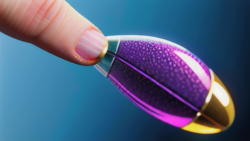ITシステム
ITシステム システムの安心守護神!ホットスタンバイとは?
- はじめに現代社会において、情報システムは私たちの生活やビジネスにとって、もはや空気や水のように欠かせない存在となっています。インターネットショッピングや銀行取引、公共サービスの利用など、あらゆる場面で情報システムが活用され、私たちの生活を支えています。しかし、どんなに高性能なシステムを構築したとしても、障害が発生する可能性はゼロではありません。 自然災害や機器の故障、あるいはソフトウェアの不具合など、予期せぬトラブルによってシステムが停止してしまうことがあります。もし、重要なシステムが停止してしまったら、業務が滞り、顧客に多大な迷惑をかけてしまうだけでなく、企業の信用を失墜させることにもなりかねません。このような事態を避けるためには、システムの安定稼働を支える技術を導入し、障害発生時にもサービスを継続できる体制を整えておくことが重要です。そのための有効な手段の一つとして、「ホットスタンバイ」という技術があります。ホットスタンバイとは、簡単に言うとシステムの複製を準備しておき、メインシステムに障害が発生した場合、すぐに予備システムに切り替えることで、サービスの停止時間を最小限に抑える仕組みです。ホットスタンバイは、システムの安定稼働を支える重要な技術です。次の章からは、ホットスタンバイの仕組みやメリット、具体的な構成例などを詳しく解説していきます。