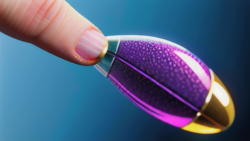ITシステム
ITシステム システムの高可用性を実現する「クラスタリング」
- クラスタリングとはクラスタリングとは、複数のものを共通の特徴に基づいてグループ分けすることを指します。これは、まるで果物の種類ごとに籠に分けるように、似た性質のもの同士を集めていく作業に似ています。ITの分野では、このクラスタリングは、複数のコンピューターを繋ぎ合わせて、あたかも一台の強力なコンピューターのように機能させる技術を指します。 このように複数のコンピューターを連携させることで、一台だけでは処理しきれないような大規模な計算処理や、大量のデータへのアクセスが可能になります。クラスタリングには、大きく分けて二つの目的があります。 一つは、処理能力の向上です。複数のコンピューターで作業を分担することで、全体としての処理速度を大幅に向上させることができます。もう一つは、システム全体の稼働率向上です。もし、一台のコンピューターに障害が発生した場合でも、他のコンピューターが処理を引き継ぐことで、システム全体としては稼働し続けることが可能になります。このように、クラスタリングは、現代のITシステムにおいて欠かせない重要な技術となっています。