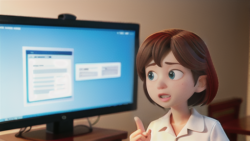ITシステム
ITシステム Web高速化の立役者:キャッシュとは?
インターネットや様々なソフトが使われる現代において、「キャッシュ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。 キャッシュとは、一度アクセスした情報を、コンピュータ本体や外部の記録装置に一時的に保存しておく仕組みのことです。 この仕組みを利用することで、同じ情報が必要になった際に、遠くから取りに行く手間を省き、処理を速くすることができます。例えば、インターネットでホームページを閲覧する際、画像や動画などのデータはキャッシュに保存されます。 このため、同じページに再度アクセスする際には、これらのデータはコンピュータや記録装置に保存されたものから読み込まれるため、ページの表示が速くなります。キャッシュは、インターネットの閲覧だけでなく、様々なソフトにおいても活用されています。 例えば、文書作成ソフトでは、編集中の文書が自動的にキャッシュに保存されることで、万が一のソフトの終了時にも、それまでの作業内容が失われないようになっています。キャッシュは、私たちが意識することなく、快適なデジタルライフを支える重要な役割を担っています。日ごろ何気なく利用しているサービスの裏側では、キャッシュの仕組みが活躍していることを少し意識してみると、また違った視点で情報技術の世界を見ることができるかもしれません。