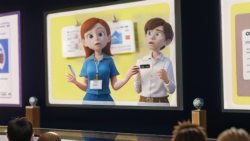 SNS
SNS 今さら聞けない?SNSとは何か、その特徴を解説
- SNSとは「SNS」とは、「ソーシャルネットワーキングサービス」を省略した言葉です。インターネットを通じて、利用者同士がつながり、情報を共有したり、交流したりすることができるサービスのことを指します。代表的なSNSとしては、短い文章や写真、動画を投稿して共有する「ツイッター」、実名での登録が基本で、友だちや家族との交流を目的とした「フェイスブック」、写真や短い動画の投稿に特化した「インスタグラム」、メッセージアプリとして日本で広く普及している「ライン」、短い動画を投稿、共有する「ティックトック」など、さまざまなサービスがあります。これらのSNSは、単に人と人とのつながりを生み出すだけでなく、企業が商品やサービスの情報を発信したり、消費者と直接的にコミュニケーションをとったりする場としても活用されています。また、近年では、個人が自身の活動や作品を発信し、共感を得ることで影響力を持つ「インフルエンサー」と呼ばれる人々も登場しており、SNSは情報発信の手段として、ますますその重要性を増しています。

















