在庫移動を効率化するSTOとは?

ICTを知りたい
先生、「STO」ってなんですか?

ICT研究家
「STO」は「ストック・トランスポート・オーダー」の略で、在庫を別の場所に移動させるための指示書のことだよ。例えば、A店に商品が不足しているときに、B店から商品を送る場合に使うね。

ICTを知りたい
なるほど。では、STOはどのように使うのですか?

ICT研究家
STOは、システム上で作成して、移動させる商品の種類や数量、送り先などを指定するんだ。そうすると、担当者がその指示に従って商品を移動させてくれるんだよ。
STOとは。
「ICT関係の言葉で『STO』ってのがあります。これは『在庫転送オーダー』の略で、簡単に言うと、ある倉庫から別の倉庫へ在庫を移動する指示のことです。 普段、商品を買うときに使う発注書と同じような形式で、移動元と移動先、移動する商品、数量などを指定します。この『STO』を使うことで、在庫の移動をスムーズに進めることができるんです。」
STOとは
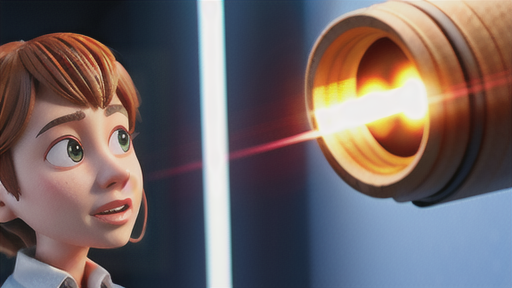
– 在庫転送オーダーSTOとはSTOは、”Stock Transport Order”の略称で、日本語では「在庫転送オーダー」と呼ばれます。これは、複数の事業拠点を持つ企業が、拠点間で効率的に在庫を移動させるために使用する仕組みです。例えば、ある製品を扱う企業が、A店とB店という2つの店舗を持っているとします。A店でその製品の在庫が不足し、B店では在庫が余っている場合、STOを活用することで、B店からA店へ必要な数量だけをスムーズに移動させることができます。このプロセスは、単なる商品の移動にとどまりません。STOでは、在庫の移動をシステム上で記録し、各拠点の在庫状況をリアルタイムに把握できるようにします。そのため、在庫の偏りを防ぎ、欠品による機会損失や過剰在庫による保管コストの増加を抑制する効果も期待できます。さらに、STOは販売管理システムや会計システムと連携している場合が多く、在庫移動に伴う伝票処理や会計処理を自動化することも可能です。これにより、業務の効率化、人為的なミスの削減、正確な在庫管理を実現することができます。このように、STOは企業の在庫管理において、効率性と正確性を向上させるための重要な役割を担っています。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| STO | Stock Transfer Orderの略称で、日本語では「在庫転送オーダー」。複数の事業拠点を持つ企業が、拠点間で効率的に在庫を移動させるために使用する仕組み。 |
| STOのメリット | – 拠点間でスムーズに在庫移動が可能 – 在庫の偏りを防ぎ、欠品や過剰在庫を抑制 – 業務の効率化、人為的なミスの削減、正確な在庫管理を実現 |
STOのメリット

– 在庫の動きを分かりやすく管理!STOのメリットSTO(在庫転送オーダー)は、企業が持つ複数の拠点間で在庫を移動させる際に発生する、一連のプロセスを管理するためのシステムです。このシステムを導入することで、従来の電話やFAXを使った転送業務に比べて、様々な面で効率化を図ることができます。従来の方法では、在庫の移動状況を把握するために、担当者が転送元と転送先に個別に確認する必要がありました。電話やFAXでのやり取りは、情報伝達の遅延や誤解が生じやすく、正確な在庫状況を把握することが難しいという課題がありました。しかし、STOシステムを導入することで、これらの課題を解決することができます。STOシステムでは、全ての在庫情報がシステム上で一元管理されるため、転送元と転送先の在庫状況をリアルタイムで確認することができます。このリアルタイムでの情報共有により、発注ミスや遅延を減らし、円滑な在庫移動を実現することができます。また、在庫状況をリアルタイムで把握できることは、適切な在庫管理にもつながります。従来の方法では、在庫不足や過剰在庫が発生しやすいため、機会損失や保管コストの増加につながっていました。STOシステムでは、必要な時に必要な量だけを移動させることができるため、在庫の適正化を図り、コスト削減にも貢献します。このように、STOシステムは企業の在庫管理業務を効率化し、コスト削減にも貢献する有効な手段と言えるでしょう。
| 従来の方法 | STOシステム |
|---|---|
| 電話やFAXでやり取り | システム上で一元管理 |
| 情報伝達の遅延や誤解 正確な在庫状況の把握が難しい |
リアルタイムで在庫状況を確認可能 情報共有による発注ミスや遅延の減少 |
| 在庫不足や過剰在庫の発生 機会損失や保管コストの増加 |
適切な在庫管理 必要な時に必要な量だけを移動 在庫の適正化によるコスト削減 |
STOの処理の流れ

– 在庫転送オーダーの処理手順在庫転送オーダー(STO)は、企業内の異なる拠点間で在庫を移動する際に用いられる手続きです。その処理の流れは、購買発注伝票の処理手順と多くの共通点があります。まず、在庫を必要とする転送先拠点が、在庫を持っている転送元拠点に対してSTOを作成するところから始まります。このSTOには、移動を希望する品目、必要な数量、希望する移動日などの情報が記載されます。STOは、いわば転送元拠点への在庫の「移動依頼書」としての役割を果たします。STOを受け取った転送元拠点は、まず自拠点の在庫状況を確認します。STOで要求された数量の在庫を確保できるか、希望する移動日に出荷が可能かどうかなどを検討します。在庫状況に問題がなく、STOを受理できると判断した場合、転送元拠点はSTOに基づいて出荷の準備を開始します。出荷作業が完了すると、転送先拠点へ在庫が移動します。これと同時に、システム上で在庫の移動が記録され、転送元拠点の在庫は減少し、転送先拠点の在庫は増加します。これで、STOの処理はすべて完了となります。このように、STOは企業内の在庫移動を円滑に行うための重要な仕組みです。
STOと購買発注の違い

企業活動において、商品を必要な場所へ移動させることは非常に重要です。その手段として、STO(棚卸資産移動オーダー)と購買発注があります。どちらも商品を移動させるという点では共通していますが、その仕組みや用途には明確な違いが存在します。
STOは、一言で言えば、企業内の異なる拠点間で商品を移動させるための指示書です。例えば、東京本社に在庫がある商品を大阪支店へ移動させたい場合にSTOが使用されます。この際、移動する商品の所有権は変わりませんが、在庫の移動を正確に記録・管理するためにSTOが作成されます。
一方、購買発注は、企業が外部の仕入先に対して商品を購入する際に発行する注文書です。必要な商品を必要な数量だけ仕入れるために、購買発注は欠かせません。購買発注に基づいて商品が納品されれば、企業間で所有権が移転し、金銭の支払いも発生します。
このように、STOと購買発注は、それぞれ異なる目的と場面で利用されます。両者を正しく理解し、適切に使い分けることで、企業はより効率的かつ正確な在庫管理を実現できるでしょう。
| 項目 | STO | 購買発注 |
|---|---|---|
| 定義 | 企業内の異なる拠点間で商品を移動させるための指示書 | 企業が外部の仕入先に対して商品を購入する際に発行する注文書 |
| 目的 | 企業内の在庫移動 | 企業外部からの商品調達 |
| 対象 | 自社内の異なる拠点 | 外部の仕入先 |
| 所有権の移転 | 発生しない | 発生する |
| 金銭の支払い | 発生しない | 発生する |
まとめ

– まとめ
複数の事業拠点を持つ企業にとって、在庫を効率的に管理することは、事業全体の成否を左右する重要な要素です。従来の在庫管理では、拠点ごとに在庫を抱え、必要な時に外部から調達するケースが多く見られました。しかし、この方法では、過剰な在庫を抱えたり、逆に在庫不足に陥ったりするリスクが常に存在します。
このような課題を解決するのが、STO(拠点間在庫移動)という考え方です。STOとは、ある拠点で在庫が余っている場合に、それを必要とする別の拠点に移動させることで、会社全体の在庫を最適化し、在庫切れや機会損失を最小限に抑えることができる仕組みです。
STOを導入することで、在庫の可視化が進み、適切なタイミングで必要な量の在庫を移動させることが可能になります。その結果、在庫保管にかかるコスト削減、輸送コストの削減、欠品による機会損失の削減など、様々なメリットを享受することができます。
在庫管理システムの導入を検討する際には、STO機能が搭載されているかどうかも重要なポイントとなります。STO機能が充実したシステムを導入することで、より効率的かつ効果的な在庫管理を実現し、企業の競争力強化につなげることができるでしょう。
| 従来の在庫管理 | 拠点間在庫移動(STO) |
|---|---|
| 拠点ごとに在庫を抱え、必要時に外部から調達 | 在庫が余っている拠点から、必要とする拠点へ移動 |
| 過剰在庫や在庫不足のリスク | 会社全体の在庫を最適化し、在庫切れや機会損失を最小限に抑える |
| – | 在庫の可視化、適切な在庫移動によるコスト削減、機会損失の削減などのメリット |
