業務効率化の鍵!MROとは?

ICTを知りたい
ICTに関連する用語『MRO』って、何のことですか?

ICT研究家
『MRO』は、もともとは工場などで使われていた言葉で、機械の修理や維持に必要なものをまとめて表す言葉なんだ。例えば、工具や部品、燃料などがMROに当たるよ。

ICTを知りたい
じゃあ、それがICTとどう関係しているんですか?

ICT研究家
インターネットが広まったことで、MROに必要なものをインターネットでまとめて買うサービスが出てきたんだ。文房具や事務用品なども、インターネットで効率的に購入できるようになったんだよ。
MROとは。
「情報通信技術に関連した言葉、『MRO』について説明します。『MRO』は、業務で使う消耗品や、その購入管理、効率化を目指す仕組みのことです。元々は製造業で使われていた言葉で、『保守』『修理』『稼働』に必要な備品を指していました。具体的には、工具、修理部品、燃料、安全を守るための資材、消耗品などが挙げられます。これらの備品は、原材料や部品とは違って種類が多く、部署ごとに必要なものを、決まった時期ではなく、何度も調達する必要があります。しかし、購入専門の部署を作るほどの量の発注はありません。そのため、担当者が自分の仕事を中断して、購入業務を行うことになり、非効率な点が問題視されていました。このような調達業務の効率化やシステム化は難しいとされてきましたが、インターネットが普及し、企業間での電子商取引が始まると状況は大きく変わりました。MROの調達支援サービスを提供する会社が現れ、インターネットを通じて調達を行う動きが広がっていったのです。そして、企業の調達業務を効率化するための取り組みとして、『MRO』という言葉が使われるようになりました。日本では、文具メーカーや通信販売会社、商社などが、文具を対象としたMRO調達システムを展開しています。紙や文具、事務機器、消耗品など、日常的に使うものを効率的に調達できるだけでなく、低価格での購入や、在庫の最適化も実現できるようになりました。」
MROの概要
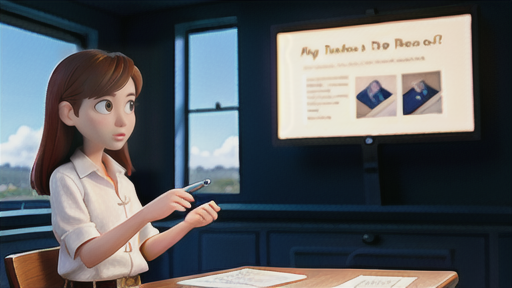
– MROの概要MROとは、「Maintenance(保守)」「Repair(修理)」「Operations(稼働)」の頭文字を取った言葉です。企業が事業を円滑に進めるためには、設備や機器を適切に維持・管理し、必要に応じて修理を行うとともに、日々の業務で必要な消耗品を適切に調達・管理する必要があります。MROは、まさにこれらの活動を包括的に捉え、効率化するためのシステムを指します。元々は製造業において、工場で稼働する設備の維持や修理に必要な工具、部品、燃料などを示す用語として使われていました。巨大な工場では、生産ラインを一刻も止めるわけにはいきません。そのため、必要な時に必要なものが迅速に調達できるよう、MROの考え方が生まれ、発展してきました。近年では、MROの対象は製造現場にとどまりません。オフィスで日常的に使用する文具やOAサプライ、事務用品などもMROに含まれるようになっています。これは、企業活動全体において、間接部門の業務効率化やコスト削減も重要視されるようになったためです。このように、MROは単なる消耗品の管理にとどまらず、企業全体の調達コストの削減や業務効率化、さらには安定稼働を支える重要な戦略として位置付けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| MROの定義 | Maintenance(保守)、Repair(修理)、Operations(稼働)の頭文字をとったもの。設備や機器の維持管理、修理、消耗品の調達・管理など、企業活動を円滑に進めるためのシステムを指す。 |
| MROの起源 | 製造業の工場において、生産ラインの安定稼働のために、必要な時に必要な工具、部品、燃料などを迅速に調達する必要性から生まれた。 |
| MROの対象範囲 | 従来は製造現場の設備や資材が中心だったが、近年ではオフィスで使用する文具、OAサプライ、事務用品なども含まれる。 |
| MROの重要性 | 企業活動全体において、間接部門の業務効率化やコスト削減、安定稼働を支える重要な戦略として位置付けられている。 |
MROが注目される背景

近年、企業活動において「MRO」という単語を耳にする機会が増えてきました。一体なぜ、MROはこれほどまでに注目されるようになったのでしょうか。
その背景には、企業における間接費削減への意識の高まりがあります。企業が事業活動を行う上で、原材料や製品といった直接費だけでなく、事務用品や工具、消耗品といった間接費も発生します。これらの間接費をまとめてMROと呼びます。
MROは、一つ一つの購入金額は少額ながらも、購入頻度が高く、多くの部署で必要となるため、管理を怠ると膨大な費用と時間がかかってしまいます。従来は、従業員が個別に購入依頼や発注を行っていましたが、この方法は非効率で、時間やコストがかかるだけでなく、適切な在庫管理も難しいといった課題がありました。
そこで、調達業務を効率化し、コスト削減や業務効率化を実現するために、MROの重要性が高まっているのです。MROを適切に管理することで、企業は不要な支出を抑え、限られた資源をより有効に活用することができるようになります。
| MROとは | 間接費
|
|---|---|
| 注目される背景 | 企業における間接費削減への意識の高まり |
| MROの特徴 |
|
| 従来の課題 |
|
| MROのメリット |
|
MRO導入のメリット

– 企業の収益力向上に貢献するMRO導入MRO(Maintenance, Repair and Operation)とは、企業活動において必要となる、生産設備の保守・修理・運用に必要な資材調達を指します。このMROを適切なシステムで管理することで、企業は様々な恩恵を受けることができます。まず、調達業務の効率化によるコスト削減効果が期待できます。従来の調達業務では、複数の業者から見積もりを取ったり、それぞれの業者と個別にやり取りする必要があり、多くの時間と手間がかかっていました。しかし、MROシステムを導入することで、システム上で複数の業者から簡単に価格比較を行い、一括発注することが可能になります。これにより、調達にかかる時間と費用を大幅に削減することができます。また、在庫管理の最適化による無駄な支出の抑制も大きなメリットです。従来型の在庫管理では、発注のタイミングが担当者の経験や勘に頼っていたため、需要予測が難しく、過剰な在庫を抱えてしまうケースが多く見られました。MROシステムでは、過去の使用状況や販売データなどを分析し、適切な在庫量を自動で計算してくれるため、在庫切れや過剰在庫のリスクを大幅に減らすことができます。さらに、MROシステム導入は、従業員の負担軽減と生産性向上にも繋がります。従来の煩雑な調達業務から解放されることで、従業員は本来の業務に集中できるようになり、業務効率が向上します。また、必要な時に必要なものが迅速に調達できる環境が整うことで、業務の遅延を防ぎ、生産性の向上に繋がります。このように、MROシステムの導入は、コスト削減、在庫管理の効率化、従業員満足度の向上など、多岐にわたるメリットをもたらし、企業の収益力向上に大きく貢献します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| コスト削減 | – システム上での一括発注による調達業務の効率化 – 価格比較の容易化 |
| 無駄な支出の抑制 | – 過去の使用状況や販売データに基づいた適切な在庫管理 – 在庫切れや過剰在庫リスクの軽減 |
| 従業員負担軽減と生産性向上 | – 調達業務の効率化による本来業務への集中 – 迅速な調達による業務遅延の防止 |
MROシステムの進化と普及

近年、あらゆるモノがインターネットにつながる時代となり、企業間取引においても電子商取引が活発化しています。このような状況下、企業の運営に必要な間接材の調達を効率化するMROシステムも、目覚ましい進化を遂げています。
かつては、電話やファックスを使って備品の発注を行っていた時代もありました。しかし、インターネットの普及により、状況は一変しました。今では、発注から納品、請求処理に至るまで、すべてのプロセスをインターネット上で一元管理できるシステムが主流となっています。
さらに、近年では、人工知能や膨大なデータの分析技術を活用した、より高度なMROシステムが登場しています。これらのシステムは、過去の購買データなどを自動的に分析し、最適な発注時期や発注量を提案してくれるなど、従来のシステムにはなかった機能を備えています。そのため、企業は、自社の規模や業務内容、課題に合わせて、最適なシステムを選ぶことができるようになっています。
日本国内においても、文具メーカーや商社などが、文具や事務用品に特化したMRO調達システムを開発、提供しており、多くの企業で導入が進んでいます。これらのシステムの導入により、企業は、間接材の調達にかかる業務を大幅に削減し、業務の効率化やコスト削減を実現できるようになります。
| 時代 | MROシステムの特徴 |
|---|---|
| かつて | 電話やファックスを使って備品の発注 |
| 現在 | 発注から納品、請求処理までをインターネット上で一元管理 |
| 近年 | AIやデータ分析を活用し、最適な発注時期や発注量を提案 |
今後のMROの展望

– 今後のMROの展望
企業活動を支える縁の下の力持ちであるMRO(Maintenance, Repair and Operation)。
今後は、モノのインターネットや人工知能といった技術革新の波に乗り、MROはさらに進化を遂げると予想されています。
例えば、あらゆる機器に搭載されたセンサーから集まる稼働データを活用することで、消耗品の在庫状況を自動的に把握し、必要なタイミングで自動的に発注するシステムの構築が可能になります。これは、従来の人手による管理に比べて、発注忘れや在庫不足による業務の遅延を防ぎ、業務効率化に大きく貢献することが期待されます。
さらに、人工知能が過去の購入履歴や需要予測に基づいて、最適な調達計画を立案するシステムも考えられます。これは、必要なものを必要な時に必要なだけ調達することを可能にし、在庫管理の効率化だけでなく、コスト削減にも繋がる可能性を秘めています。
また、MROシステムと他のシステムとの連携も、今後の大きな流れとなるでしょう。例えば、企業資源計画(ERP)システムやサプライチェーンマネジメント(SCM)システムと連携することで、サプライチェーン全体の可視化・効率化を図ることができます。
このように、MROは、企業の競争力を強化する上で、ますます重要な要素となっていくと考えられています。
| MROの進化 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| IoT/センサー活用 | 機器の稼働データによる在庫状況把握、自動発注 | 発注忘れ・在庫不足防止、業務効率化 |
| AI活用 | 過去のデータに基づく最適な調達計画 | 在庫管理効率化、コスト削減 |
| 他システム連携 | ERP/SCMとの連携によるサプライチェーン全体の可視化・効率化 | – |
