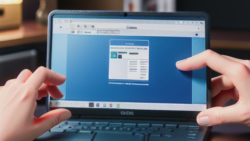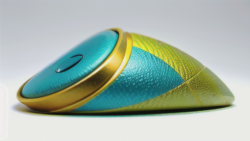コンサル
コンサル コンサル業界の平仄:資料作成の極意
「平仄(ひょうそく)」という言葉の由来についてお話しましょう。もともとは中国から伝わった言葉で、漢詩の世界で使われていました。漢詩のルールでは、音の上がり下がりである「声調」を、句の中で一定の規則に従って配置する必要があるのですが、この規則や、そこから生まれる音の調和のことを「平仄」と呼んでいたのです。
時代が流れ、現代では「平仄」は、単に音の調和という意味だけでなく、「つじつまが合うこと」「道理にかなっていること」「筋道が通っていること」といった意味合いでも使われるようになりました。
特に、コンサルティング業界など、論理的な思考や表現が求められる分野では、「平仄が合う」という表現が頻繁に登場します。資料作成の際などに、「この説明は平仄が合っているだろうか?」「もっと平仄の合った説明にできないか?」といった具合に、内容の整合性や論理の妥当性を確認するために使われているのです。