ユニバーサルデザイン:すべての人に優しい社会を実現する

ICTを知りたい
先生、『ユニバーサルデザイン』って、みんなに優しいデザインってことはわかったんですけど、バリアフリーとは何が違うんですか?

ICT研究家
いい質問だね!確かにどちらも暮らしやすさを目指している点では同じだけど、考え方が少し違うんだ。バリアフリーは、例えば、階段に後からスロープを付けることで、車いすの人も移動できるようにする考え方だね。

ICTを知りたい
あ!後から付け足すか、最初からそう作るかの違いってことですか?

ICT研究家
その通り!ユニバーサルデザインは、最初からスロープのある建物を作ることで、みんなが初めから使いやすいように設計する考え方なんだよ。
ユニバーサルデザインとは。
「情報通信技術に関係する言葉である『ユニバーサルデザイン』について説明します。『ユニバーサルデザイン』とは、建物や道具などを、できるだけたくさんの人が使いやすいように工夫して作るという考え方のことです。『ユニバーサルデザイン』は『UD』と略して書くこともあります。国や育った環境、年齢や性別、障がいの有無に関係なく、すべての人を対象としていることが特徴です。似た言葉に『バリアフリー』があります。『バリアフリー』は、障がいのある人や高齢者が暮らしにくいと感じるものを取り除くという考え方です。『ユニバーサルデザイン』は、あらかじめ不便なところができないように設計するという点で、『バリアフリー』と関係があります。
ユニバーサルデザインとは

– ユニバーサルデザインとはユニバーサルデザイン(UD)とは、年齢や性別、国籍、文化、障がいの有無などに関わらず、できるだけ多くの人にとって使いやすい製品、建物、環境などをデザインする考え方です。例えば、段差のない入り口や色のコントラストがはっきりした表示は、車いすを使う人だけでなく、高齢者やベビーカーを押す人にとっても便利です。また、音声案内や分かりやすいピクトグラムは、視覚に障がいのある人だけでなく、日本語が理解できない外国人にとっても役立ちます。ユニバーサルデザインは、特定の人だけに向けたものではなく、すべての人が利用しやすいことを目指しています。そのため、結果的に誰もが暮らしやすい社会の実現につながります。誰もが使いやすいデザインを心がけることで、社会参加の機会が均等になり、すべての人が自分らしく生き生きと暮らせる社会を実現することができます。
| ユニバーサルデザイン(UD)とは | 具体例 | 対象者 |
|---|---|---|
| 年齢や性別、国籍、文化、障がいの有無などに関わらず、できるだけ多くの人にとって使いやすい製品、建物、環境などをデザインする考え方 |
|
|
ユニバーサルデザインの7原則
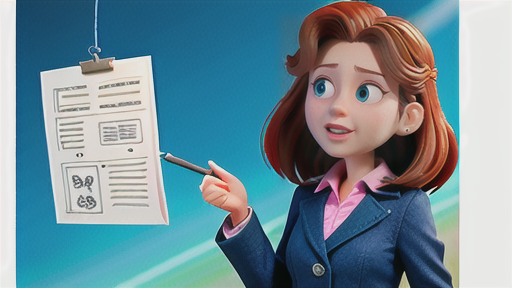
– ユニバーサルデザインの7原則
製品やサービス、環境などを設計する上で、可能な限り多くの人が快適に利用できることを目指す考え方、それがユニバーサルデザインです。このユニバーサルデザインを実現するための指針として、7つの原則が提唱されています。
1. –公平な利用–
誰もが同じように利用できる、あるいは利用しやすいように、可能な限り選択の幅を広く提供する。特定の人だけが利用できる特別な機能ではなく、最初からすべての人に開かれた設計を目指します。
2. –柔軟な利用–
利用者の能力や好みに合わせて、様々な方法で利用できる自由度が高いデザインが求められます。例えば、右利きの人も左利きの人も使いやすい道具や、様々な言語に対応した情報提供などが挙げられます。
3. –使いやすさ–
経験や知識、言語能力、集中力などに関わらず、誰でも簡単に理解し、直感的に使えるようにデザインする必要があります。複雑な操作や専門知識を必要とせず、迷わずに利用できることが重要です。
4. –分かりやすさ–
利用者に必要な情報を、分かりやすく伝達する必要があります。視覚的な案内表示や音声ガイドなど、複数の感覚に訴えることで、より多くの人に情報を伝えることができます。
5. –安全性–
不注意や誤操作によって、利用者が危険な目に遭ったり、怪我をしたりすることがないよう、安全性を考慮した設計が必要です。また、万が一事故が起きた場合でも、被害を最小限に抑えられるような工夫も求められます。
6. –無理のない身体負担–
長時間使用しても疲れにくい、身体への負担が少ないデザインであることが重要です。無理な姿勢を強いることなく、自然な動作で利用できるよう、人間工学に基づいた設計が求められます。
7. –適切な大きさ・空間–
年齢や体格、障害の有無に関わらず、誰もがアクセスしやすく、利用しやすいように、適切な大きさや空間を確保する必要があります。例えば、車椅子でも移動しやすい通路幅や、様々な身長の人が使いやすい高さに設置された設備などが挙げられます。
これらの原則を考慮することで、年齢や性別、障害の有無、文化や国籍の違いを超えて、より多くの人にとって使いやすい製品、サービス、環境などを実現することができます。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 公平な利用 | 誰もが同じように利用できる、あるいは利用しやすいように、可能な限り選択の幅を広く提供する。 |
| 柔軟な利用 | 利用者の能力や好みに合わせて、様々な方法で利用できる自由度が高いデザイン。 |
| 使いやすさ | 経験や知識、言語能力、集中力などに関わらず、誰でも簡単に理解し、直感的に使えるデザイン。 |
| 分かりやすさ | 利用者に必要な情報を、分かりやすく伝達する。複数の感覚に訴えることで、より多くの人に情報を伝える。 |
| 安全性 | 不注意や誤操作によって、利用者が危険な目に遭ったり、怪我をしたりすることがないよう、安全性を考慮した設計。 |
| 無理のない身体負担 | 長時間使用しても疲れにくい、身体への負担が少ないデザイン。人間工学に基づいた設計。 |
| 適切な大きさ・空間 | 年齢や体格、障害の有無に関わらず、誰もがアクセスしやすく、利用しやすいように、適切な大きさや空間を確保する。 |
バリアフリーとの違い

– バリアフリーとの違いユニバーサルデザインと混同されやすい概念にバリアフリーがあります。どちらも暮らしやすい環境作りを目指すものですが、そのアプローチは異なります。バリアフリーは、主に障がいのある人が感じる物理的な障壁を取り除くことを目的としています。例えば、階段にスロープを付けたり、点字ブロックを設置したりすることが挙げられます。 一方、ユニバーサルデザインは、最初からあらゆる人が使いやすいデザインを目指します。年齢、性別、障害の有無、文化や言語の違いなどに関わらず、全ての人が快適に利用できることを目指すのです。バリアフリーは、既存の施設や製品に後から手を加えることが多いです。そのため、どうしても「付け足し」という印象になりがちです。一方、ユニバーサルデザインは、設計段階からあらゆる人を考慮するため、より自然で美しいデザインになることが多いです。バリアフリーが事後的な対応であるのに対し、ユニバーサルデザインは最初からすべての人を考慮する、より包括的な考え方と言えるでしょう。
| 項目 | バリアフリー | ユニバーサルデザイン |
|---|---|---|
| 対象 | 主に障がいのある人 | すべての人(年齢、性別、障害の有無、文化や言語の違いなどに関わらず) |
| 目的 | 物理的な障壁を取り除く | 最初からあらゆる人が使いやすいデザイン |
| 例 | 階段にスロープ、点字ブロックの設置 | 設計段階からあらゆる人を考慮したデザイン |
| 特徴 | 事後的な対応になりがち、「付け足し」という印象 | 自然で美しいデザインになりやすい、最初からすべての人を考慮する、より包括的な考え方 |
身近なユニバーサルデザインの例

私たちは日常生活の中で、意識せずに多くのユニバーサルデザインに触れ、その恩恵を受けています。例えば、歩道に段差が無く、緩やかに傾斜しているスロープを見たことがあるでしょう。これは、車椅子の方やベビーカーを押す方にとって移動の妨げにならないようにという配慮から生まれたデザインです。また、お店や施設の入り口でよく見かけるスライドドアも、ユニバーサルデザインの一例です。高齢の方や体の不自由な方にとって、重いドアを開け閉めすることは大変な作業ですが、スライドドアであれば軽く触れるだけで開閉できるため、誰でも楽に利用できます。さらに、駅や公共施設などで見かける案内表示には、色のコントラストがはっきりとしたものが多く使われています。これは、色覚に障がいのある方にも情報が伝わりやすいようにという配慮からです。このように、ユニバーサルデザインは、特定の人のためだけでなく、すべての人にとって暮らしやすい社会を実現するために、重要な役割を担っているのです。
| ユニバーサルデザインの例 | 誰にとっての配慮か |
|---|---|
| スロープ | 車椅子の方、ベビーカーを押す方 |
| スライドドア | 高齢の方、体の不自由な方 |
| 色のコントラストがはっきりとした案内表示 | 色覚に障がいのある方 |
ユニバーサルデザインの未来

近年、情報通信技術の著しい進歩により、あらゆる人が快適に利用できることを目指すユニバーサルデザインは、これまで以上に大きな可能性を秘めています。
特に、人の声を理解する音声認識技術や、写真や映像の内容を判別する画像認識技術、そして人間の学習能力や思考能力を模倣した人工知能技術の発展は目覚ましく、従来の方法では難しかった多様なニーズへの対応を可能にしています。
例えば、視覚に障害を持つ人々は、音声認識技術を用いることで、音声で指示を出して家電製品を操作したり、画面の情報を音声で読み上げてもらったりすることができます。また、聴覚に障害を持つ人々は、画像認識技術によって、手話を読み取って音声に変換するアプリケーションや、周囲の音を文字で表示するシステムの恩恵を受けることができます。さらに、人工知能は、個々のユーザーの身体的な特徴や認知能力、状況に合わせて、ウェブサイトやアプリケーションの表示方法や操作方法を自動的に調整することも可能です。
このように、情報通信技術の進化は、ユニバーサルデザインの実現を大きく前進させると共に、年齢や性別、障害の有無に関わらず、すべての人が暮らしやすい社会の実現に向けた、重要な鍵となるでしょう。
| 技術 | 説明 | ユニバーサルデザインへの応用 |
|---|---|---|
| 音声認識技術 | 人の声を理解する技術 | – 音声で家電製品を操作 – 画面情報を音声で読み上げ |
| 画像認識技術 | 写真や映像の内容を判別する技術 | – 手話を読み取って音声に変換 – 周囲の音を文字で表示 |
| 人工知能技術 | 人間の学習能力や思考能力を模倣した技術 | – ユーザーに合わせて表示方法や操作方法を自動調整 |
