下請法:公正な取引のために

ICTを知りたい
先生、『下請法』って言葉をよく聞くんですけど、ICTと何か関係があるんですか?

ICT研究家
良い質問ですね。実は大いに関係があります。特に情報システムの開発や運用など、ICTを使った仕事の発注を受けることが多いからです。

ICTを知りたい
そうなんですね!具体的にどんな時に関係してくるんですか?

ICT研究家
例えば、ウェブサイト制作やソフトウェア開発を依頼されたとします。その際、下請法は、発注者と受注者の間で、仕事の依頼内容や報酬の支払いについて、書面できちんと取り決めをしなさい、と定めています。これは、トラブルを防ぐためにとても重要なことです。
下請法とは。
情報通信技術に関係する言葉の一つに「下請け法」があります。これは正式には「下請け代金支払い遅延等防止法」という法律です。大きな会社が力 relations力で弱い立場にある会社に不利な取引をさせないように、両者の取引が公平に行われるように、そして弱い立場にある会社の利益を守ることを目的としています。この法律は、市場における競争が正しく自由に行われるように定められた「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、つまり独占禁止法を補うものとして、1956年に作られました。
下請け法で対象となる取引は、「製造を依頼する」「修理を依頼する」「情報に関する成果物の作成を依頼する」「サービスの提供を依頼する」の4種類です。これらの取引では、依頼する側には、依頼する時に法律で決められた書面をすぐに渡す義務、品物などを受け取ってから60日以内に支払い日を伝える義務、取引内容を書いた書類を作って保管しておく義務、支払いが遅れた場合に遅延分の利息を支払う義務などがあります。また、依頼する側は、品物の受け取りを拒否することや、支払い期日を遅らせること、支払う金額を少なくすること、返品すること、無理な値段で購入させること、無理やり購入や利用をさせること、仕返しをすること、材料費などの支払いを早くさせること、値引きが難しい書類を渡すこと、不当な利益を求めること、依頼内容を不当に変更することややり直しをさせることは禁止されています。
下請け法に違反した場合、依頼する側が違反に気づいていたかどうか、弱い立場にある会社が同意していたかどうかに関係なく、公正取引委員会から注意を受けることがあります。注意を受けた場合、原則として注意を受けた会社の名前や違反内容などが公表されます。もし、弱い立場にある会社が受けた被害が小さかったり、違反の可能性がある場合には、指導が行われることもあります。書面を渡す義務や書類を作って保管する義務に違反した場合は、違反した会社の代表者や担当者などに対し、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
下請法とは

– 下請法とは「下請法」とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」と呼ばれる法律で、規模の大きい企業と中小企業との間の取引において、公正な関係を築くことを目的としています。日本の製造業では、大きな企業が最終製品を製造する際に、部品の製造や加工を中小企業に依頼する、いわゆる「下請け」という構造が広く見られます。しかし、このような関係では、大きな企業がその力関係を利用して、中小企業に不利な取引を強いるケースも見られました。そこで、下請法では、弱い立場になりがちな中小企業を保護するために、大きな企業がしてはいけない行為を具体的に定めています。例えば、製品の納期に関して、無理に納期を早めるよう強要することや、一方的に納品価格を引き下げる行為は禁止されています。また、発注した製品の納品を受けたにも関わらず、正当な理由なく支払いを遅らせることも禁止されています。下請法は、中小企業が安心して事業を継続し、日本経済全体の活性化を図るために重要な役割を担っています。
| 法律名 | 目的 | 対象 | 禁止事項 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 下請代金支払遅延等防止法(下請法) | 規模の大きい企業と中小企業との間の取引において、公正な関係を築くこと | 日本の製造業における下請け構造 (大企業が中小企業に部品製造や加工を依頼する関係) |
– 無理な納期の強要 – 一方的な納品価格の引き下げ – 正当な理由のない支払いの遅延 |
中小企業が安心して事業を継続し、日本経済全体の活性化を図る |
独占禁止法との関係
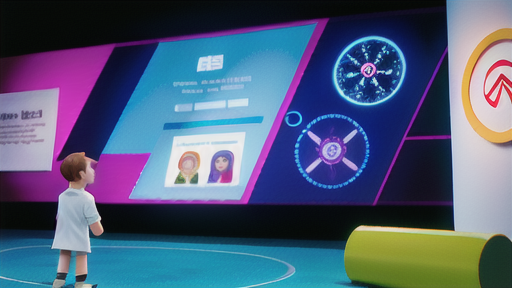
– 独占禁止法との関係下請法は、1956年に制定された法律で、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。この法律は、独占禁止法を補完するものとして生まれました。では、独占禁止法とはどのような法律なのでしょうか。独占禁止法は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という正式名称を持つ法律です。この法律は、市場において、企業が公正かつ自由に競争することを阻害する行為を広く禁止しています。これは、健全な市場経済を維持し、消費者の利益を守るために非常に重要なことです。しかし、規模の大きな企業と、その企業から仕事を請け負う小さな企業との間では、独占禁止法だけでは十分に規制できない不公正な取引が行われてしまう可能性があります。そこで、下請法は、親事業者と下請事業者間における取引に焦点を当て、その取引の中で起こりうる不公正な行為をより具体的に規制することで、公正な取引環境の実現を目指しています。例えば、親事業者が優越的な立場を利用して、下請事業者に対して不当に低い価格で仕事を請け負わせたり、一方的に契約内容を変更したりすることを禁止しています。このように、下請法は、独占禁止法だけではカバーしきれない部分を補完することで、あらゆる企業にとって公正な取引環境を作り出すことを目的としているのです。
| 法律 | 目的 | 対象 | 下請法との関係 |
|---|---|---|---|
| 独占禁止法 (正式名称: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) |
市場における 企業の公正かつ自由な競争の確保 |
市場における 企業間の取引 |
・下請法は独占禁止法を補完する法律 ・独占禁止法だけでは規制できない、親事業者と下請事業者間の不公正な取引を規制 |
| 下請法 (正式名称: 下請代金支払遅延等防止法) |
親事業者と下請事業者間の取引における 不公正な行為の規制による 公正な取引環境の実現 |
親事業者と 下請事業者間の取引 |
– |
対象となる取引

– 対象となる取引
事業を円滑に進めるために、他社に業務の一部を委託することはよくあることです。しかし、委託する側と受託する側の立場には、どうしても力の差が生じがちです。このような状況下では、不当な要求や不利益が生じる可能性も否定できません。そこで、弱い立場にある事業者を保護するために制定されたのが下請法です。
下請法が適用されるのは、具体的に「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4種類の取引です。
* -製造委託-製品の製造や部品の加工などを他社に依頼する場合です。
* -修理委託-製品や機械の修理などを他社に依頼する場合です。
* -情報成果物作成委託-ソフトウェア開発やデザイン制作などを他社に依頼する場合です。
* -役務提供委託-翻訳やデータ入力、システム運用などを他社に依頼する場合です。
これらの取引は、いずれも親事業者が下請事業者に業務を委託し、その成果物を提供してもらうという構造を持っています。そして、このような力関係の不均衡から生じる不公正な行為を防ぐために、下請法はこれらの取引を対象としています。
下請法は、親事業者による一方的な契約内容の変更や、不当に低い報酬、支払い遅延などを禁じています。そして、違反した場合には罰則も規定されています。 下請事業者は、安心して取引を行うために、下請法の内容をよく理解しておくことが重要です。
| 取引の種類 | 内容 |
|---|---|
| 製造委託 | 製品の製造や部品の加工などを他社に依頼する場合 |
| 修理委託 | 製品や機械の修理などを他社に依頼する場合 |
| 情報成果物作成委託 | ソフトウェア開発やデザイン制作などを他社に依頼する場合 |
| 役務提供委託 | 翻訳やデータ入力、システム運用などを他社に依頼する場合 |
親事業者の義務

– 親事業者の義務下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、取引において優位な立場にある親事業者に対し、下請事業者を守るための様々な義務を定めています。まず、取引の開始時に、親事業者は下請法第3条に基づく書面を下請事業者に交付しなければなりません。この書面には、作業内容、納期、価格、支払い方法など、取引条件を具体的に記載する必要があります。これは、口約束ではなく、書面によって取引条件を明確化することで、後々のトラブルを未然に防ぐことを目的としています。また、親事業者は、下請事業者から物品等の納入を受けた後、60日以内に支払期日を定める義務があります。これは、下請事業者が不当に長期間、代金の支払いを待たされることを防ぐためのものです。さらに、支払いが遅れた場合には、遅延利息を支払う義務も負います。親事業者は、下請取引の内容を記載した書類を作成し、一定期間保存することも義務付けられています。具体的には、いつ、どのような内容の取引を、いくらで行ったのかを記録した書類を作成し、これを3年間保存しなければなりません。これは、万が一トラブルが発生した場合に、証拠となる書類を確保しておくことで、問題解決をスムーズに進めることを目的としています。これらの義務を怠ると、公正取引委員会から勧告や指導を受け、場合によっては罰金が科されることもあります。 親事業者は、下請法の規定をよく理解し、下請事業者との取引において、常に法令を遵守するよう心がける必要があります。
| 親事業者の義務(下請法) | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 書面交付義務 | 取引開始時に、作業内容、納期、価格、支払い方法など、取引条件を書面に記載して交付する。 | 口約束を防ぎ、取引条件を明確化することで、後々のトラブルを未然に防ぐ。 |
| 支払期日設定・遅延利息支払義務 | 物品等の納入後、60日以内に支払期日を定める。支払いが遅れた場合には遅延利息を支払う。 | 下請事業者が不当に長期間、代金の支払いを待たされることを防ぐ。 |
| 書類作成・保存義務 | 下請取引の内容を記載した書類を作成し、3年間保存する。 | トラブル発生時に、証拠となる書類を確保することで、問題解決をスムーズに進める。 |
親事業者の禁止行為

– 親事業者の禁止行為事業を円滑に進めるためには、取引関係にある事業者同士が対等な立場で、公正な取引を行うことが何よりも大切です。しかし、事業規模や経済力に大きな差があると、立場が強い側がその力を不当に利用して、弱い立場にある事業者に不利な条件を押し付けてしまう可能性があります。こうした問題を防ぎ、公正な取引を確保するために、下請法では親事業者が行ってはならない行為を具体的に定めています。親事業者による禁止行為は全部で11項目ありますが、いずれも親事業者がその優越的な立場を利用して、下請事業者に不利益を強いる行為であり、具体的には次の様な行為が挙げられます。* 正当な理由がないのに、下請事業者からの製品や部品の受け取りを拒む行為* あらかじめ決められた納期を守っているにも関わらず、一方的に納品を拒む行為* 下請事業者との合意なしに、一方的に下請代金を減額する行為* 納品した製品や部品の検査を行う際、必要以上に時間をかけたり、無理な理由をつけて不合格にしたりする行為* 下請事業者に対して、自社の製品やサービスの購入、利用を強制する行為* 下請事業者が他の事業者と取引することを妨げる行為これらの禁止行為に違反した場合、親事業者には罰則が科せられる可能性があります。下請取引においては、常に公正な取引を心がけ、法律で定められたルールを遵守することが重要です。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 受取拒否 | 正当な理由がないのに、下請事業者からの製品や部品の受け取りを拒む行為 |
| 納品拒否 | あらかじめ決められた納期を守っているにも関わらず、一方的に納品を拒む行為 |
| 下請代金の減額 | 下請事業者との合意なしに、一方的に下請代金を減額する行為 |
| 不当な検査 | 納品した製品や部品の検査を行う際、必要以上に時間をかけたり、無理な理由をつけて不合格にしたりする行為 |
| 自社製品等の購入・利用の強制 | 下請事業者に対して、自社の製品やサービスの購入、利用を強制する行為 |
| 取引の妨害 | 下請事業者が他の事業者と取引することを妨げる行為 |
違反した場合の罰則

下請法は、取引における優位な立場を利用して不当な要求を行うことを禁じる法律です。この法律に違反した場合、公正取引委員会から様々な措置が講じられます。
違反企業に対しては、まず公正取引委員会から勧告がなされます。勧告とは、違反行為を是正するために公正取引委員会が企業に対して行うものです。勧告を受けた企業名は公表されるため、企業 reputationに影響が出る可能性も考慮しなければなりません。
勧告よりも軽い処分として、指導があります。これは、違反のおそれがある場合などに行われます。
さらに、違反内容によっては、罰則が科されることもあります。特に、「書面の交付義務」や「書類の作成・保存義務」といった、書面による取引の透明性を確保するための規定に違反した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
このように、下請法には、違反行為に対する罰則規定が設けられています。親事業者は、下請事業者との取引において、法令を遵守し、公正な取引に努める必要があります。
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 勧告 | 違反行為を是正するために行われる | 企業名は公表される |
| 指導 | 違反のおそれがある場合などに行われる | |
| 罰則 | 違反内容によっては、罰則が科される | 例:書面の交付義務違反⇒50万円以下の罰金 |
