システム移行をスムーズに!マイグレーションの基礎知識

ICTを知りたい
『マイグレーション』って、具体的にどんなことをするのか、いまいちピンと来ないんですけど…

ICT研究家
例えば、スマートフォンを買い替えたときのことを想像してみて。新しいスマホでも前のスマホで使っていたアプリを使いたいよね?その時に、アプリのデータを移したり、設定をやり直したりするだろう?あれもマイグレーションの一種なんだよ。

ICTを知りたい
ああ、なんとなく分かってきました!アプリだけじゃなくて、もっと大きなシステムとかでもやるってことですか?

ICT研究家
その通り!企業で使っているような大規模なシステムでも、OSが古くなったり、機能が足りなくなったりしたら、新しいシステムに移行する必要があるんだ。その時に、データや設定を新しいシステムに移し替える作業もマイグレーションって呼ばれているんだよ。
マイグレーションとは。
「情報通信技術に関連して使われる『マイグレーション』という言葉があります。これは、ソフトウェアやシステム、データを、異なる基本ソフトなど、別の環境に移したり、新しい環境で再び設定し直したりすることを指します。普段は、古い基本ソフトで使っていたソフトウェアやデータを、新しい基本ソフトでも使えるように入れ替えることを意味します。このほかにも、プログラム開発などで、新しい環境でも使えるように変換することや、データベースのデータを新しい環境で動かせるようにすることも『マイグレーション』に含まれます。ちなみに、この言葉は英語の『移住』を意味する言葉からきています。」
マイグレーションとは
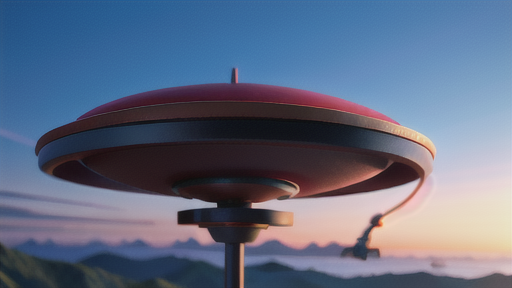
– マイグレーションとは「マイグレーション」とは、コンピューターのシステムやソフトウェア、データを、別の環境に移したり、新しい環境に合わせて設定し直したりすることを指します。 身近な例では、パソコンを買い替えた時が挙げられます。古いパソコンで使っていた文書作成ソフトや保存していた写真データを新しいパソコンに移し、使えるようにする作業もマイグレーションの一つです。企業で使われているシステムでも、マイグレーションは頻繁に行われています。パソコンと違い、企業のシステムは規模が大きく、複雑なものが多いため、マイグレーションには専門的な知識と技術が必要です。では、なぜ企業はシステムのマイグレーションを行う必要があるのでしょうか?その理由はいくつかあります。まず、OSやハードウェアの老朽化です。長年使用していると、システムの動作が遅くなったり、故障のリスクが高まったりします。このような事態を防ぎ、安定したシステム運用を続けるために、新しいOSやハードウェアに対応した環境へ移行する必要があります。次に、機能の拡張が挙げられます。企業は事業の拡大や変化に合わせて、システムに新しい機能を追加する必要が生じることがあります。既存のシステムでは対応できない場合、より高機能なシステムへ移行することで、業務効率の向上や新たなサービスの提供が可能になります。さらに、コスト削減の面も挙げられます。古いシステムを維持し続けるよりも、新しいシステムに移行することで、運用コストや保守コストを削減できる場合があります。このように、マイグレーションは企業にとって、安定した事業成長を維持していくために欠かせないものです。しかし、マイグレーションは、データ移行の失敗やシステムの停止など、リスクを伴う作業でもあります。そのため、事前に綿密な計画と準備を行い、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが重要です。
| マイグレーションの定義 | コンピューターのシステムやソフトウェア、データを、別の環境に移したり、新しい環境に合わせて設定し直したりすること |
|---|---|
| 身近な例 | パソコンを買い替えた時に、古いパソコンのデータやソフトを新しいパソコンに移す作業 |
| 企業システムにおけるマイグレーションの必要性 |
|
| マイグレーションのリスク | データ移行の失敗やシステムの停止など |
| マイグレーションを成功させるために | 事前に綿密な計画と準備を行い、専門家のサポートを受けながら慎重に進める |
マイグレーションが必要となるケース

– マイグレーションが必要となるケース情報システムの移行であるマイグレーションは、様々な状況で必要となります。ここでは、代表的なケースをいくつか詳しく見ていきましょう。まず、避けて通れないのが、使用している基本ソフト(OS)のバージョンアップに伴うマイグレーションです。基本ソフトは、コンピューターシステム全体を管理する土台となるソフトウェアです。このバージョンアップは、機能追加や性能向上のために定期的に行われますが、古いバージョンは開発元のサポートが終了し、セキュリティ上のリスクが高まる可能性があります。そのため、新しいバージョンに対応した環境へ、情報システム全体を移行する必要が生じるのです。次に、ハードウェアの更改もマイグレーションが必要となるケースです。サーバーや記憶装置といったハードウェアは、経年劣化によって性能が低下したり、故障のリスクが高まったりします。そこで、これらの老朽化したハードウェアを新しいものに入れ替える際に、情報システム全体を新しい環境に移行する必要が生じます。さらに、企業の合併や業務効率化に伴うシステム統合も、マイグレーションが必要となるケースです。複数の企業が合併する場合や、企業内で別々のシステムを使用している場合、それぞれ独立した情報システムを統合することで、業務効率化やコスト削減を図ることができます。このシステム統合の際にも、既存のシステムを新しい統合システムへ移行する必要があり、大規模なマイグレーションとなるケースもあります。このように、マイグレーションは様々な場面で必要となり、その規模や複雑さも状況によって大きく異なります。しかし、いずれの場合も、情報システムの安定稼働を維持し、業務への影響を最小限に抑えるためには、綿密な計画と準備が不可欠です。
| マイグレーションが必要となるケース | 詳細 |
|---|---|
| OSのバージョンアップ |
|
| ハードウェアの更改 |
|
| 企業の合併や業務効率化に伴うシステム統合 |
|
マイグレーションの種類

– マイグレーションの種類システムやデータを移行するマイグレーションには、その規模や手法によっていくつかの種類があります。ここでは、代表的な3つの方法について詳しく見ていきましょう。-# リホストリホストは、既存のシステムをほぼそのままの形で、新しい環境に移行する方法です。「リロケーション」と呼ばれることもあります。例えるなら、家具の配置や内装はそのままに、異なる場所へ引っ越しをするようなイメージです。この方法の最大のメリットは、比較的容易で、費用を抑えられる点です。システムに変更を加える必要がないため、移行に伴うリスクも低く、短期間で完了できます。しかし、新しい環境の性能や機能を十分に活かせない可能性があります。古いシステム構成のまま移行するため、期待通りの性能向上などが得られないケースも考えられます。-# リプラットフォームリプラットフォームは、既存システムの一部を変更し、新しい環境に移行する方法です。例えば、これまでとは異なる種類のサーバーやOSへ移行する際に、アプリケーションはそのままで、データ形式だけを変換するなどが考えられます。リホストと比較して、新しい環境への適合性を高めることができます。システム全体を刷新する必要がないため、リライトよりもコストを抑えつつ、新しい環境の利点を一部享受できるというメリットがあります。-# リライトリライトは、既存のシステムを全く新しい技術を用いて再構築する方法です。システムの土台から作り直すため、最新の技術やアーキテクチャを採用できます。この方法の最大のメリットは、システムの性能や拡張性を飛躍的に向上できる点です。最新の技術を取り入れることで、将来的な需要の変化にも柔軟に対応できます。しかし、他の方法と比較して、多大な費用と時間を要します。開発期間の長さから、計画段階で綿密な準備と検討が必要です。
| 種類 | 説明 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| リホスト | 既存システムをほぼそのまま新しい環境に移行 | – 比較的容易 – コストを抑えられる – リスクが低い – 短期間で完了 |
– 新環境の性能や機能を十分に活かせない可能性 – 期待通りの性能向上などが得られないケースも |
| リプラットフォーム | 既存システムの一部を変更し新しい環境に移行 | – 新環境への適合性を高める – コストを抑えつつ、新環境の利点を一部享受できる |
– リライトと比較してメリットは少ない |
| リライト | 既存システムを全く新しい技術を用いて再構築 | – システムの性能や拡張性を飛躍的に向上 – 最新の技術を取り入れ、将来的な需要の変化にも柔軟に対応 |
– 多大な費用と時間がかかる – 綿密な準備と検討が必要 |
マイグレーションの手順

システム移行は、一般的に計画から運用までの六つの段階を経て行われます。
最初の計画段階では、現在のシステム環境の状況や移行によって達成したい目的、クリアすべき要件を明確にします。これらの要素を踏まえて、具体的な移行計画を策定します。
次の設計段階では、計画に基づき、新しい環境の設計を行います。データの移行方法や手順の詳細、移行スケジュールなどを決定します。
構築段階では、設計に基づき、新しい環境の構築やデータ移行の準備を行います。新しいハードウェアやソフトウェアの導入、データの移行ツールなどの準備を行います。
テスト段階では、構築が完了した新しい環境で、システムが正常に動作することを確認するためのテストを実施します。
移行段階では、テストが完了したら、いよいよ実際の移行作業を行います。システムの停止時間を最小限に抑えるよう、計画的に作業を進めます。
最後の運用段階では、新しい環境でのシステム運用を開始します。移行後もシステムが安定稼働するよう監視を行い、問題が発生した場合は速やかに対応します。
これらの手順は、移行の内容や規模によって異なり、必ずしも全ての工程が必要となるわけではありません。しかし、円滑なシステム移行を実現するためには、それぞれの工程をしっかりと計画し、実行することが重要です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 計画 | – 現状分析 – 目的・要件定義 – 移行計画策定 |
| 設計 | – 新環境設計 – データ移行方法・手順決定 – 移行スケジュール決定 |
| 構築 | – 新環境構築 – データ移行準備 – ハードウェア・ソフトウェア導入 |
| テスト | – 新環境でのシステム動作確認 |
| 移行 | – 実際の移行作業実施 – システム停止時間の最小化 |
| 運用 | – 新環境でのシステム運用開始 – システム監視 – 問題発生時の対応 |
マイグレーションの注意点

– マイグレーションの注意点システム移行をスムーズに行うためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。まず、移行作業全体の計画を綿密に立て、十分な時間的余裕を持つことが大切です。システムの規模や複雑さによって作業量は大きく変わるため、予想以上に時間がかかることを想定しておくべきです。準備不足のまま計画を進めると、スケジュールに遅れが生じたり、予期していなかった問題が発生したりする可能性が高まります。余裕を持ったスケジュールを立てることで、問題が発生した場合でも冷静に対処できるようになります。次に、移行によって影響を受ける範囲を正確に把握する必要があります。影響範囲はシステムの規模が大きくなるほど広範囲に及ぶため、関係部署との連携を密にし、事前に調整をしておくことが不可欠です。円滑なコミュニケーションを通じて関係者全員が移行内容を正しく理解することで、混乱を防ぎ、スムーズな移行を実現できます。さらに、移行後のテストは決して手を抜かず、十分に実施する必要があります。テストが不十分なまま本番環境に移行してしまうと、システムが正常に動作せず、業務に大きな支障をきたす可能性があります。データが正しく移行されているか、システムの処理速度は問題ないかなど、様々な観点から入念に確認し、問題がないことを確認してから本番環境への移行を行うようにしましょう。
| マイグレーションの注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 綿密な計画と時間的余裕 | システムの規模や複雑さに応じた十分な時間的余裕を持った計画を立てる。 |
| 影響範囲の正確な把握 | 関係部署と連携し、影響範囲を明確化し、事前に調整を行う。 |
| 十分な移行後テストの実施 | データ移行の確認、処理速度など、様々な観点から入念にテストを実施する。 |
