データを守る!RAID技術の基礎知識

ICTを知りたい
先生、「RAID」ってなんですか?コンピューターの授業で出てきたんですけど、よく分からなくて…

ICT研究家
「RAID」は、複数の記憶装置を組み合わせて、まるで一つの大きな記憶装置のように見せる技術のことだよ。たとえば、パソコンに複数のハードディスクを取り付けて、まとめて管理するのに使われるんだ。

ICTを知りたい
へえー、そうなんですね。でも、複数の記憶装置を組み合わせるメリットって何かあるんですか?

ICT研究家
いい質問だね!RAIDを使うと、データを複数の記憶装置に分散して保存できるから、読み書きが速くなるんだ。しかも、もしもの時に備えて、同じデータを複数の場所に保存することもできるから、安全性も高まるんだよ。
RAIDとは。
「情報通信技術に関係する言葉、『レイド』について説明します。『レイド』とは、複数のハードディスクなどの記憶装置を、まるで一つの大きな記憶装置のように扱えるようにする技術のことです。
複数の記憶装置にデータを分散して保存することで、データの読み書きが速くなるだけでなく、もしもの時に備えて故障への強さも増します。
データの分散の仕方によって、速さや故障への強さのレベルが異なり、『レイド0』から『レイド6』までの7種類に分類されます。」
RAIDとは

– RAIDとはRAID(Redundant Array of Independent Disks)とは、複数のハードディスクを組み合わせて、あたかも一つの大きなディスクのように扱う技術のことです。読み方は「レイド」です。 RAIDを構築することで、データの冗長化による耐障害性の向上、複数ディスクへの並列アクセスによる高速化、大容量化など、様々なメリットを得られます。 従来、ハードディスクは精密機器であるがゆえに故障のリスクがつきものでした。もし、重要なデータが入ったハードディスクが故障してしまうと、データが失われ、業務に大きな支障をきたす可能性があります。 RAIDは、このようなハードディスクの故障リスクを軽減するために開発されました。RAIDには、データの保持方法や処理速度、信頼性などが異なるレベル0から6までの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。 例えば、RAID0は高速化に重点を置いた方式ですが、耐障害性はありません。 一方で、RAID1はデータの複製を保持するため、高い耐障害性を実現できますが、容量効率は悪くなります。このように、RAIDのレベルによってメリット・デメリットは異なるため、システムの要件に合わせて適切なレベルを選択する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| RAIDとは | 複数のハードディスクを組み合わせて、あたかも一つの大きなディスクのように扱う技術 |
| メリット | – データの冗長化による耐障害性の向上 – 複数ディスクへの並列アクセスによる高速化 – 大容量化 |
| RAIDのレベル | レベル0~6まであり、データの保持方法や処理速度、信頼性などが異なる。 レベルによってメリット・デメリットが異なるため、システム要件に合わせて適切なレベルを選択する必要がある。 |
| RAIDレベルの例 | – RAID0:高速化重視、耐障害性なし – RAID1:高い耐障害性、容量効率が悪い |
RAIDの仕組み
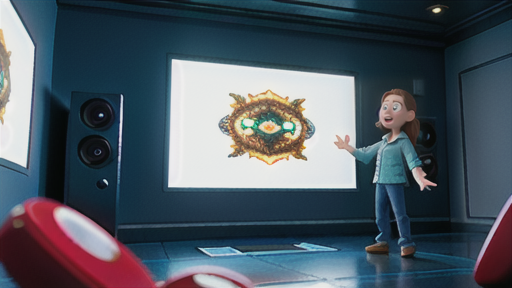
RAIDは、複数のハードディスクをあたかも一つの大きなディスクのように扱う技術です。これにより、高速化や耐障害性向上など、様々なメリットを実現できます。
RAIDにはいくつかの種類があり、それぞれデータの分散や保存方法が異なります。
例えば、「RAID 0」と呼ばれる方式では、データを複数のディスクに交互に書き込むことで、高速化を実現します。これは、一つのデータを複数のディスクに同時に書き込めるため、書き込み処理全体にかかる時間を短縮できるためです。しかし、この方式はデータを分散して保存するだけで、複製を作成しないため、もし一つのディスクが故障してしまうと、全てのデータが失われてしまうという欠点があります。
一方、「RAID 1」と呼ばれる方式では、同じデータを複数のディスクに同時に書き込みます。そのため、仮に一つのディスクが故障しても、他のディスクに同じデータが残っているため、データの消失を防ぐことができます。しかし、この方式は常に同じデータを複数のディスクに書き込むため、容量効率が悪くなってしまうという欠点があります。
このように、RAIDには様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。そのため、実際にRAIDを構築する際には、用途や目的に合わせて最適なRAIDを選択する必要があります。
| RAIDの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| RAID 0 | データを複数のディスクに交互に書き込む | 高速化 | 耐障害性が低い(1台のディスク故障で全データ消失) |
| RAID 1 | 同じデータを複数のディスクに同時に書き込む | 耐障害性が高い(1台のディスク故障でもデータ維持可能) | 容量効率が悪い |
RAIDのレベル

– RAIDのレベルRAIDとは、複数のハードディスクを組み合わせて1つのドライブとして扱う技術です。データ保護や処理速度向上などを目的として利用されます。RAIDにはレベルと呼ばれる種類があり、それぞれデータの分散方法や冗長化の方法が異なります。そのため、用途に合わせて最適なレベルを選択することが重要になります。-# 高速化に特化したRAID0RAID0は、データを複数のハードディスクに分散して書き込むことで、読み書きの速度を向上させるレベルです。データを分割して書き込むため、1つのハードディスクに書き込む場合と比べて高速に処理できます。ただし、RAID0はデータを二重に保存する仕組みを持たないため、1つのハードディスクに障害が発生すると、全てのデータが失われてしまいます。そのため、速度を重視する一方で、データの安全性は低いという特徴があります。主に、動画編集など一時的に大容量のデータを扱う場合に適しています。-# 耐障害性に特化したRAID1RAID1は、2台のハードディスクに同じデータを書き込むことで、データを保護するレベルです。一方のハードディスクに障害が発生しても、もう一方のハードディスクからデータを読み取ることができるため、高い安全性を誇ります。ただし、RAID1はデータを二重に保存するため、実際に使用できる容量は半分になります。そのため、データの安全性を重視する一方で、容量効率は低いという特徴があります。主に、OSや重要なデータなど、データの消失が許されない場合に適しています。-# 高速性と耐障害性を両立させたRAID5RAID5は、データを複数のハードディスクに分散して書き込むと同時に、パリティと呼ばれるエラー訂正情報も一緒に書き込むレベルです。1台のハードディスクに障害が発生した場合でも、残りのハードディスクとパリティ情報から、失われたデータを復元できます。RAID5はRAID0とRAID1の両方の利点を兼ね備えており、高速性と耐障害性のバランスが取れているという特徴があります。主に、データベースサーバーなど、ある程度の速度と安全性の両方が求められる場合に適しています。このように、RAIDには様々なレベルが存在し、それぞれに異なる特徴があります。それぞれのレベルの特徴を理解した上で、用途に合わせて適切なレベルを選択することが重要です。
| RAIDレベル | 特徴 | メリット | デメリット | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| RAID0 | ストライピング データを複数のディスクに分散して書き込む |
高速な読み書きが可能 | 耐障害性がなく、1台のディスク故障で全データ消失 | 動画編集など、一時的に大容量データを扱う場合 |
| RAID1 | ミラーリング データを2台のディスクに同じ内容を書き込む |
高い耐障害性 1台のディスク故障時でもデータ保全可能 |
容量効率が低い 実質的な容量は半分になる |
OSや重要データなど、データ消失が許されない場合 |
| RAID5 | ストライピング+パリティ データとパリティ情報を複数のディスクに分散して書き込む |
高速性と耐障害性のバランス 1台のディスク故障時でもデータ復元可能 |
RAID0より速度が劣る RAID1より容量効率が良い |
データベースサーバーなど、速度と安全性の両方が求められる場合 |
RAIDのメリット

– RAIDの利点RAIDを採用する利点は、大きく分けて高速化、耐障害性の向上、大容量化の3つが挙げられます。-# 高速化RAIDでは、複数の記憶装置を組み合わせて利用することで、データの読み書きを並列処理できます。1台の記憶装置だけに読み書きを集中させる場合と比べて、処理を分散できるため、全体的な処理速度の向上が見込めます。この高速化は、特にデータベースのように、大量のデータへのアクセスが発生する状況下において大きな効果を発揮します。-# 耐障害性の向上RAIDの構成によっては、データを複数の記憶装置に分散して保存することで、万が一1台の記憶装置に障害が発生した場合でも、データの消失を防ぐことができます。このようなデータ保護の仕組みは、特に重要なデータを取り扱うシステムにおいて、安心感をもたらします。-# 大容量化複数の記憶装置を1つの大きな記憶領域として扱うことで、大容量化を実現できます。1台あたりの容量が限られている記憶装置でも、複数台を組み合わせることで、より多くのデータを保存できるようになり、容量不足の解消に役立ちます。
| 利点 | 説明 |
|---|---|
| 高速化 | 複数の記憶装置によるデータ読み書きの並列処理で高速化を実現。データベースのような大量データアクセス環境で効果を発揮。 |
| 耐障害性の向上 | データ分散保存により、記憶装置の障害発生時にもデータ消失を防止。重要なデータを取り扱うシステムに安心感を与える。 |
| 大容量化 | 複数記憶装置を統合的に利用することで大容量化を実現。記憶装置単体の容量制限を解消し、容量不足の解消に貢献。 |
RAIDの選び方

– RAIDの選び方データ保管の方式として知られるRAIDには、複数の種類があり、それぞれに特徴があります。そのため、自身の利用環境や目的に最適なRAIDを選択することが重要となります。RAIDを選ぶ際には、まず用途を明確にしましょう。例えば、動画編集のように大容量データの高速な読み書きが必要な場合は、RAID 0が適しています。RAID 0は複数の記憶装置を並列化して扱うことで、高速な処理を実現します。ただし、データの冗長性を持たないため、1つの装置に障害が発生すると全てのデータが失われるリスクがあります。一方、サーバーのようにデータの安全性を重視する場合は、RAID 1やRAID 5が適しています。RAID 1は同じデータを2つの装置に同時に書き込むことで、1つの装置に障害が発生してもデータを守ることができます。RAID 5はデータを分散して書き込み、さらにパリティと呼ばれる誤り訂正情報も記録することで、より高い安全性と記憶効率を実現します。予算も重要な要素です。RAID 0は比較的安価に構築できますが、RAID 1やRAID 5はより多くの記憶装置が必要となるため、コストがかかります。また、RAIDを構築するには、対応したRAIDコントローラーが必要となる場合があります。RAIDコントローラーは、RAIDの構成や管理を行うための装置です。マザーボードによっては、RAID機能が内蔵されている場合もありますが、より高度なRAIDを構築する場合は、別途RAIDコントローラーを購入する必要があります。このように、RAIDには様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。自身の用途や予算、必要な信頼性などを考慮して、最適なRAIDを選びましょう。
| RAIDの種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 (ストライピング) | データを複数のドライブに分散して書き込む | 高速な読み書き速度 | 耐障害性がない(1台のドライブ故障で全データ消失) | 動画編集、画像編集など高速な読み書きが必要な用途 |
| RAID 1 (ミラーリング) | データを2台のドライブに同じ内容を書き込む | 高い耐障害性(1台のドライブ故障時でもデータ復旧可能) | 容量効率が悪い(2倍の容量が必要) | サーバー、重要なデータ保管などデータの安全性を重視する用途 |
| RAID 5 (パリティ付きストライピング) | データを複数のドライブに分散して書き込み、パリティ情報も追加 | RAID 0とRAID 1のメリットを組み合わせたタイプ 比較的高い耐障害性と高速な読み書き速度 |
RAID 0よりは速度が劣る RAID 1よりは容量効率が良い |
データベースサーバー、ファイルサーバーなど、速度と安全性のバランスを取りたい用途 |
RAIDの注意点
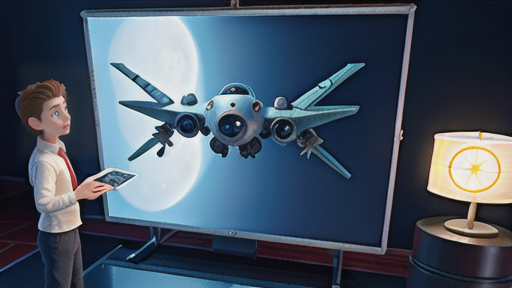
RAIDは、データを保護し、ストレージシステムの信頼性を高めるための有効な手段ですが、万能ではありません。導入前にいくつかの注意点を押さえておく必要があります。
まず、RAIDはデータ消失に対する万能薬ではないことを理解する必要があります。RAIDは、主にハードディスクの物理的な故障によるデータ損失を防ぐための技術です。人為的なミス、ウイルス感染、自然災害など、他の要因によるデータ消失を防ぐことはできません。
次に、RAIDを構築すると、データの冗長化のためにディスク容量の一部が使用されるため、実際に使用できる容量は減少します。使用するRAIDレベルによって、使用可能な容量は異なります。例えば、RAID 1 の場合は、全体のディスク容量の半分が冗長化に使用されます。
また、RAIDレベルによっては、ディスク障害発生時の復旧に時間がかかる場合があります。特に、大容量のディスクを使用している場合や、RAID 5 や RAID 6 のようにパリティ情報を複雑に計算する必要がある場合は、復旧に時間がかかる可能性があります。
これらの注意点に加え、RAIDの構築や運用には専門的な知識が必要となる場合もあります。そのため、RAIDの導入を検討する際には、事前に十分な調査を行い、専門家の意見を聞くなどして、慎重に進めることが重要です。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| データの保護 ストレージシステムの信頼性向上 |
|
