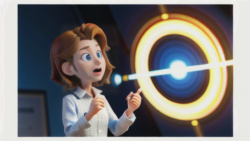IT
IT キッティングとは?業務効率化の鍵
- キッティングとは? 「キッティング」とは、情報通信技術(ICT)の分野において、コンピューターや周辺機器などを組み立て、設定を行い、すぐに使える状態にする作業のことです。元々は製造業などで使われていた言葉で、製品を組み立てるために必要な部品をまとめておくことを指していました。そこから転じて、ICTの分野でも使われるようになりました。具体的には、コンピューター本体にOSやソフトウェアをインストールしたり、周辺機器を接続して動作確認を行ったり、ネットワークに接続するための設定を行ったりといった作業が含まれます。キッティングを行うことで、利用者はコンピューターや周辺機器を個別に設定する手間が省け、すぐに使い始めることができます。また、企業においては、大量のコンピューターを効率的に導入することが可能になります。近年では、テレワークの普及などにより、企業が従業員にパソコンやタブレット端末などを貸与するケースが増加しています。このような場合にも、キッティングは欠かせない作業となっています。