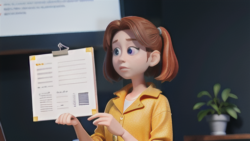IT
IT TCOって何?企業の賢いIT投資を解説
「総所有コスト」は、英語の「Total Cost of Ownership」を省略したもので「TCO」と呼ばれます。これは、新たにコンピューターシステムを導入してから、運用し、最終的に廃棄するまでの長い期間を通して、どれだけの費用が掛かるのかを表すものです。従来の考え方では、コンピューターシステムを導入する際に、機器そのものの購入費用にばかり目が行きがちでした。しかし、「TCO」という考え方では、機器の購入費用だけでなく、システムを導入する際にかかる費用や、実際に運用していく中で発生する費用、さらには、不要になったシステムを廃棄する際に発生する費用など、あらゆる費用を考慮する必要があります。例えば、システムを導入する際には、機器の設置費用や設定費用、ソフトウェアの購入費用、担当者の教育費用など、様々な費用が発生します。また、運用していく中で、システムの保守や管理、ソフトウェアのアップデート、障害対応などにも費用が掛かります。そして最終的には、システムが不要になった際に、データの消去や機器の廃棄などの費用も発生します。このように、「TCO」は、コンピューターシステムに関わる費用全体を把握し、長期的な視点でコスト削減を検討していく上で非常に重要な考え方と言えるでしょう。