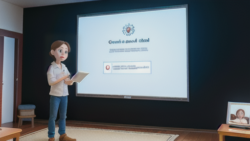IT
IT 企業の進化を支えるシステムインテグレーション
- システムインテグレーションとは
企業が成長していくためには、顧客のニーズを素早くつかみ、変化の激しい社会環境に柔軟に対応していく必要があります。そのために重要な役割を担うのが、企業の業務全体を効率化し、円滑な事業運営を支える情報システムです。
システムインテグレーションとは、それぞれの企業が抱える経営課題や事業目標を達成するために、個別の業務プロセスや情報ニーズに合わせて最適な情報システムを設計・構築するサービスのことです。
複数の異なるシステムを連携させて、データの一元管理や業務の自動化を実現することで、業務効率の向上、コスト削減、意思決定の迅速化など、さまざまな効果が期待できます。
いわば、システムインテグレーションとは、企業の成長戦略を具現化するための、強力な武器と言えるでしょう。