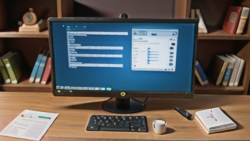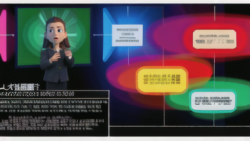ITシステム
ITシステム ネットワークの信頼性と速度を向上させるNICチーミングとは
コンピューターやネットワーク機器には、ネットワークに接続するための部品であるネットワークインターフェースカードが搭載されています。このネットワークインターフェースカードは、略してNICとも呼ばれます。一台の機器に複数のNICを搭載している場合に、これらのNICを仮想的に一つにまとめる技術のことをNICチーミングと呼びます。
NICチーミングを行うことで、複数のNICをあたかも一つのNICのように扱うことが可能になります。これは、ネットワークの可用性、速度、全体的なパフォーマンスを向上させるために非常に有効な手段です。
例えば、複数のNICを束ねて帯域幅を増やすことで、ネットワーク全体の速度を向上させることができます。また、一つのNICに障害が発生した場合でも、他のNICが機能することで、ネットワークの接続を維持することができます。 このように、NICチーミングは、ネットワークの信頼性と性能を向上させるための重要な技術と言えるでしょう。