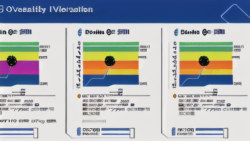ITシステム
ITシステム OTM:分散システムの心臓部
- OTMとはOTMは、ObjectTransactionalMiddlewareまたはObjectTransactionMonitorの略称で、複数のシステムやアプリケーションが連携して動作する、いわゆる分散アプリケーション環境において欠かせないソフトウェアです。従来のORB (Object Request Broker) は、異なるシステム間でのオブジェクトのやり取りを仲介する役割を担っていましたが、トランザクション処理については考慮されていませんでした。OTMは、このORBにトランザクション制御機能を統合することで、より信頼性と拡張性の高い分散アプリケーション環境を実現しました。OTMの大きな特徴は、複数のシステムやアプリケーションが関わる処理の一貫性を確保できる点です。例えば、銀行の口座振替システムを考えてみましょう。Aさんの口座からBさんの口座へお金を振り込む場合、Aさんの口座からの引き落としと、Bさんの口座への入金の両方が正常に完了しなければなりません。もし、どちらか一方だけが完了した場合、データの不整合が発生し、顧客に損害を与える可能性があります。このような問題を防ぐために、OTMはトランザクションの概念を用います。トランザクションとは、一連の処理をまとめて一つの作業単位として扱う仕組みです。口座振替の例では、Aさんの口座からの引き落としとBさんの口座への入金を一つのトランザクションとして扱い、両方が正常に完了した場合のみ、処理を確定します。もし、どちらか一方に失敗した場合、処理全体を取り消し、データの整合性を保ちます。このように、OTMは、分散アプリケーション環境において、データの整合性と処理の一貫性を保証する重要な役割を担っています。