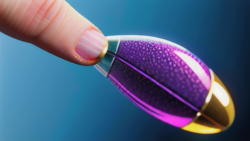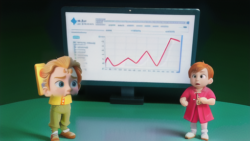ITシステム
ITシステム 営業とマーケ連携を強化!Pardotとは
顧客との繋がりを深める上で、顧客関係管理は企業にとって非常に重要な要素となっています。そんな中、セールスフォースが提供する法人向けマーケティングオートメーションソリューションであるPardotが注目されています。Pardotは、企業のマーケティング活動を自動化し、効率化することで、見込み客の獲得から顧客との関係構築、そして最終的な売上拡大までを支援します。では、Pardotは具体的にどのようなことができるのでしょうか?Pardotは、メールマーケティング、ランディングページ作成、フォーム作成、マーケティングキャンペーン管理、リードナーチャリング、リードスコアリング、投資対効果分析などの機能を提供しています。これらの機能を詳しく見ていきましょう。まず、Pardotは企業の顧客ターゲットに合わせたメールの一斉送信や、ウェブサイトへの訪問者を顧客候補に変えるための専用ページの作成、顧客情報を得るためのアンケートフォーム作成などを可能にします。さらに、Pardotは、マーケティングキャンペーンの効果を最大化する為の管理機能や、顧客候補を育成するための情報提供の自動化、顧客候補の購買意欲を数値化する機能なども備えています。加えてPardotは、マーケティング活動が売上目標の達成にどのように貢献したかを分析する機能も備えています。これらの機能により、マーケティング部門は、顧客一人ひとりに合わせた最適な情報を最適なタイミングで届けることができるようになり、顧客との繋がりをより一層深めることができるのです。