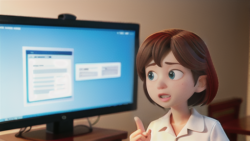ITシステム
ITシステム プラットフォーム:ソフトウェアの舞台裏
私たちは普段、スマートフォンやパソコンを使って、様々なソフトウエアを操作しています。画面に映し出される文字や画像、聞こえてくる音など、ソフトウエアは私たちの視覚や聴覚に直接訴えかけてくるため、その存在を意識しやすいものです。しかし、その裏側では、目に見えない多くの要素が複雑に絡み合いながら、ソフトウエアを支えています。ソフトウエアが正しく動くためには、それを支える土台となる「基盤」が必要です。この基盤は、例えるならば舞台のようなものです。舞台の上で役者が躍動するように、ソフトウエアも基盤の上でこそ、その能力を最大限に発揮することができます。この基盤は、ハードウエアとソフトウエアを繋ぐ、橋渡し的な役割を担っています。ハードウエアは、パソコン本体やスマートフォンなど、実際に触ることができる物理的な装置のことです。基盤は、ソフトウエアがハードウエアを制御するための共通の言葉を提供することで、両者の仲立ちをします。例えるならば、外国人と会話する際に通訳が必要なように、ソフトウエアとハードウエアも、直接やり取りをするためには「通訳」が必要です。基盤は、ソフトウエアとハードウエアがお互いに理解し合えるよう、「通訳」となって、円滑なコミュニケーションを支えているのです。