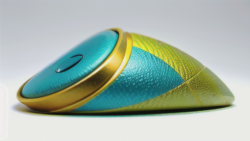ITシステム
ITシステム ネットワークの門番!ポート番号を理解しよう
私たちの身の回りにあるコンピュータは、インターネットや会社のネットワークを通じて、様々な情報をやり取りしています。この時、情報の行き先を特定するために使われるのが「ポート」です。情報をやり取りする際に、コンピュータは宛先を「IPアドレス」で特定しますが、そのコンピュータ上でも複数のプログラムが同時に動作していることがあります。例えば、インターネットを見たり、メールを送ったりといった作業は、それぞれ異なるプログラムによって行われます。そこで、どのプログラムに情報を届けるのかを区別するために、ポートが使われるのです。ポートは番号で管理されており、よく使われるサービスには、あらかじめ番号が決められています。例えば、ウェブサイトを閲覧する際に使われる「HTTP」という通信方式では、通常「80番ポート」が使われます。私たちがウェブサイトを見ることができるのは、このポートを通じて情報が送られてくるからです。このように、ポートはネットワーク上の情報の行き先を特定するための重要な役割を果たしており、インターネットや社内ネットワークを支える基盤技術の一つと言えるでしょう。