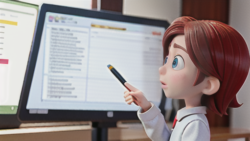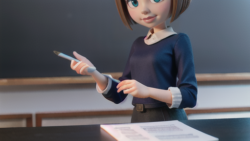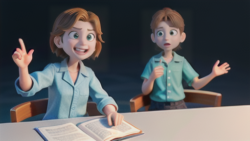会計
会計 企業統治の要!SOX法入門
- アメリカで生まれた企業改革法アメリカで2002年に成立した「上場企業会計改革および投資家保護法」、通称SOX法は、企業の不正会計を防止し、投資家を保護することを目的とした法律です。この法律が制定された背景には、2000年代初頭にアメリカで起きた大規模な企業会計スキャンダルがあります。当時、エネルギー大手エンロンや通信 giant ワールドコムといった大企業で、粉飾決算を含む大規模な会計不正が相次いで発覚しました。これらの事件は、アメリカ経済全体に大きな衝撃を与え、企業の財務報告に対する信頼が大きく揺らぎました。このような事態を重く受け止め、アメリカ政府は企業の会計処理の透明性を高め、投資家を守るための抜本的な改革に乗り出しました。その結果誕生したのがSOX法です。SOX法では、企業の財務報告の正確性を担保するために、経営者による財務報告書の証明責任を強化したほか、会計監査の独立性と厳格性の向上、内部統制の評価と報告制度の整備など、多岐にわたる改革が盛り込まれました。SOX法は、成立当初こそ、その厳格さから企業に過大な負担を強いるとの批判もありました。しかし、その後、企業会計の透明性向上や投資家保護に大きく貢献したと評価されており、現在では、アメリカのみならず、世界各国の企業 governance の模範となっています。