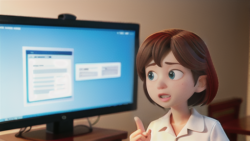開発
開発 システム開発における「導出」とは?
- 導出とは何かシステム開発の現場では、「導出」という言葉がよく使われます。これは、すでにあるデータを使って、別の新しいデータを作り出すことを意味します。言い換えれば、「どのようにその値が決まるのか」、その手順や計算方法を明確にすることです。例えば、皆さんが毎日使うカレンダーを思い浮かべてみましょう。カレンダーには、今日の日付や祝日などが書かれていますが、これらの情報は最初から決まっているわけではありません。祝日などは法律で定められていますが、実際にカレンダーに日付を表示するには、複雑な計算が必要です。このように、ある情報をもとに、計算や加工といった手順を経て、最終的な情報を得るプロセス全体を「導出」と呼びます。具体的な例として、商品の売上金額を導出してみましょう。売上金額は、販売数量と単価をかけ合わせることで計算できます。この場合、「販売数量 × 単価 = 売上金額」という計算式が、売上金額を導出するためのルールとなります。システム開発では、このような導出ルールをプログラムとして記述することで、コンピュータが自動的に情報を計算し、処理できるようにします。導出は、システム開発において非常に重要な概念です。なぜなら、システムで扱うデータの多くは、他のデータから計算や加工によって導き出されるからです。導出の概念を理解することで、システム全体の構造やデータの流れを把握することができます。これは、システム開発をスムーズに進めるために欠かせない要素と言えるでしょう。