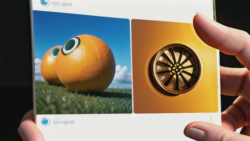ハードウェア
ハードウェア 身近な存在、液晶ディスプレイの仕組み
- 液晶ディスプレイとは液晶ディスプレイは、薄型テレビやパソコンのモニター、スマートフォンなど、私たちの生活に欠かせない様々な電子機器に搭載され、映像を表示する役割を担っています。薄くて軽く、場所を取らないという利点から、かつて主流だったブラウン管テレビに代わり、急速に普及しました。
液晶ディスプレイの最大の特徴は、電気の力で光の透過率を変化させることができる特殊な液体である「液晶」を使用している点です。液晶は、電圧をかけることで分子の向きが変わり、光の通過を制御する性質を持っています。この性質を利用して、液晶ディスプレイは、背面から照射される光を液晶で遮ったり透過させたりすることで、画面に様々な色や模様を映し出しているのです。
液晶自体は発光しないため、液晶ディスプレイの背面には、画面全体を明るく照らすためのバックライトが搭載されています。バックライトの光が液晶を通過することで、私たちは鮮明な映像を見ることができるのです。
液晶ディスプレイは、薄型軽量であることに加え、消費電力が低い、発熱量が少ないといった利点も備えています。そのため、持ち運びやすさや省エネ性能が求められるモバイル機器にも最適です。今後も、更なる高画質化、低消費電力化が進み、私たちの生活に無くてはならない存在であり続けるでしょう。