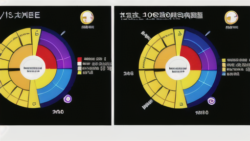 WEBサービス
WEBサービス Webサイト構築を容易にするCMSとは
- コンテンツ管理システム(CMS)の概要ウェブサイトを構築・運用する上で、専門知識がなくても容易にコンテンツを管理できる仕組みが、コンテンツ管理システム(CMS)です。CMSは、ウェブサイトの土台となるシステムを提供し、利用者はその上でテキストや画像などのコンテンツを自由に作成・編集できます。従来のウェブサイト制作では、HTMLやCSSといった専門的なプログラミング言語の知識が必須でした。しかしCMSの登場により、これらの知識がなくても、直感的な操作でウェブサイトのコンテンツを管理できるようになりました。CMSの大きな特徴は、コンテンツとデザインが分離されている点にあります。ウェブサイトのデザインはテンプレートとしてあらかじめ用意されており、利用者はコンテンツの作成に集中できます。例えば、ブログ記事を作成する場合、記事のタイトル、本文、画像などを所定の入力欄に入力するだけで、自動的にウェブサイトに反映されます。HTMLタグなどを意識する必要はありません。CMSは、ブログサイトだけでなく、企業サイトやECサイトなど、様々な種類のウェブサイトで利用されています。目的に合わせて最適なCMSを選択することが、ウェブサイトの成功に繋がります。























