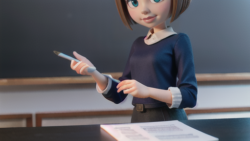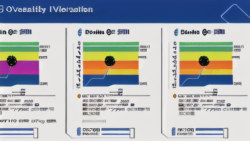情報リテラシー
情報リテラシー 広がるデジタル格差とその深刻な影響
- デジタルディバイドとは情報通信技術(ICT)の普及がめざましい昨今、誰もが当たり前に情報にアクセスできると思われがちです。しかし実際には、コンピュータやインターネットを使える人とそうでない人の間に、大きな溝が存在しています。これを「デジタルディバイド」と呼びます。デジタルディバイドは、現代社会において深刻な問題を引き起こしています。なぜなら、経済活動、教育、医療、行政サービスなど、あらゆる場面において、情報へのアクセスは必要不可欠なものだからです。情報へのアクセス機会が限られることは、社会参加の機会を奪われ、生活の質を低下させることに繋がります。では、なぜデジタルディバイドは起こるのでしょうか。その要因は複雑に絡み合っていますが、経済状況の格差は大きな要因の一つです。コンピュータやインターネットの利用には、端末の購入費用や通信費などのコストがかかります。そのため、経済的に余裕のない人々は、情報通信技術を利用するハードルが高くなってしまいます。年齢もまた、デジタルディバイドを生み出す要因となります。若い世代は、幼い頃からデジタル機器に触れる機会が多く、抵抗なく情報技術を扱える傾向があります。一方、高齢者は、新しい技術に対する苦手意識や、使い方を学ぶ機会の不足などから、情報通信技術の利用に遅れをとってしまうことがあります。さらに、都市部と地方では、情報通信網の整備状況に差がある場合があり、これもデジタルディバイドを拡大させる要因となります。高速インターネット回線が整備されていない地域では、快適にインターネットを利用することが難しく、情報へのアクセス機会が制限されてしまいます。このように、デジタルディバイドは、経済状況、年齢、地域など、様々な要因によって生じる深刻な社会問題です。情報社会において、誰もが平等に機会を得られるように、デジタルディバイドの解消に向けた取り組みが求められています。