軽減税率の基礎知識

ICTを知りたい
先生、「軽減税率」って何か教えてください。なんだか難しそうでよくわからないんです。

ICT研究家
そうだね。「軽減税率」は、簡単に言うと、みんなが使う物の値段が急に上がりすぎないように、一部の商品だけ消費税を安くする仕組みのことだよ。例えば、2019年10月から消費税が10%になった時、食べ物は8%のままになったよね。それが軽減税率のおかげなんだ。

ICTを知りたい
なるほど!じゃあ、コンビニでお弁当を買ったら8%になるってことですか?

ICT研究家
その通り!ただし、お店で食べる場合は10%になるから気を付けてね。軽減税率は、持ち帰って食べるものだけに適用されるんだ。
軽減税率とは。
令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられましたが、それを受けて、飲食料品と新聞については、消費税の税率を8%にする制度ができました。ただし、これは、お酒以外の食べ物を販売する場合と、週に2回以上発行される新聞を定期購読する場合に限られます。食べ物の販売については、持ち帰りや出前、宅配は対象になりますが、お店で食事をする場合や仕出し弁当は対象になりません。
軽減税率とは?
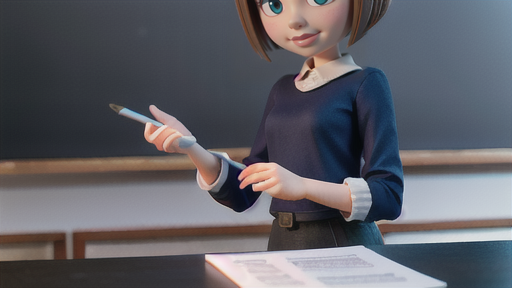
2019年10月1日、日本の多くの商品やサービスに対して課される消費税の税率が8%から10%に引き上げられました。しかし、生活必需品への影響を抑え、国民の負担を軽減するため、全ての商品やサービスが一律に10%になったわけではありません。「軽減税率」という制度が導入され、特定の商品やサービスについては、これまで通りの8%の税率が適用されることになりました。
この軽減税率の対象となるのは、主に食料品と新聞です。例えば、私たちが毎日口にする野菜、果物、肉、魚、米、パンなどは、軽減税率の対象となり8%の税率で購入することができます。ただし、飲食料品全てが対象となるわけではなく、店内で飲食する場合は10%、持ち帰りの場合は8%といったように、飲食方法によって税率が異なる場合もあります。また、新聞についても、定期購読している場合は軽減税率の対象となります。
軽減税率は、消費税増税による家計への負担を和らげ、国民の生活を守るための重要な制度です。対象となる商品やサービスをよく理解し、賢く活用していくことが大切です。
| 区分 | 対象 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽減税率 (8%) | 野菜 | 8% | |
| 果物 | 8% | ||
| 肉 | 8% | ||
| 魚 | 8% | ||
| 米、パン | 8% | ||
| 新聞 (定期購読) | 8% | ||
| 標準税率 (10%) | 飲食店での飲食 | 10% | |
| 上記以外の商品・サービス | 10% |
対象となるのは?

令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられましたが、食料品など一部の商品については軽減税率として8%に据え置かれました。では、具体的にどのようなものが軽減税率の対象となるのでしょうか?
大きく分けて、「お酒と外食を除く飲食料品」と「定期購読契約に基づいて週に2回以上発行される新聞」の二つが挙げられます。
「お酒と外食を除く飲食料品」とは、例えば、スーパーやコンビニで購入する食料品や飲み物が該当します。ただし、お酒は軽減税率の対象外なので注意が必要です。また、持ち帰りではなく、レストランで食事をしたり、出前やケータリングサービスを利用したりする場合は、「外食」とみなされるため、軽減税率は適用されず、10%の税率で購入することになります。
「定期購読契約に基づいて週に2回以上発行される新聞」とは、その名の通り、定期購読契約を結んで配達される新聞のことで、軽減税率の対象となります。しかし、書店やコンビニで購入する新聞は軽減税率の対象外なので注意が必要です。
飲食料品の線引きは?

消費税には軽減税率が適用される品目とそうでない品目があります。食料品は生活に欠かせないものとして、軽減税率の対象となっていますが、線引きが分かりにくいという声も聞かれます。そこで、今回は飲食料品の線引きについて詳しく解説します。
軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定されたものが基準となります。具体的には、普段私たちが口にする野菜や果物、肉や魚といった生鮮食品、お菓子や調味料などが該当します。これらの食品を購入する場合、消費税率は8%となります。
一方で、お酒は酒税法の対象となるため、軽減税率は適用されません。そのため、お酒を購入する際には10%の税率が適用されます。また、レストランで食事をしたり、喫茶店でコーヒーを飲んだりする「外食」も軽減税率の対象外です。
テイクアウトや出前、宅配サービスを利用する場合には注意が必要です。食品自体には軽減税率が適用されますが、容器代や配達料金などについては、それが飲食料品と明確に区分できる場合を除き、10%の税率が適用されます。例えば、お弁当を購入する場合、お弁当の中身は軽減税率の対象となりますが、容器や配達料は10%の税率となるケースが多いです。
飲食料品の線引きは複雑な場合もあるため、判断に迷う場合は国税庁のホームページなどを参考にしてみてください。
| 分類 | 内容 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽減税率対象(8%) | 野菜、果物、肉、魚などの生鮮食品 | 8% | 食品表示法の対象 |
| お菓子、調味料 | 8% | 食品表示法の対象 | |
| テイクアウト、出前、宅配サービスの食品自体 | 8% | 食品表示法の対象 | |
| 軽減税率非対象(10%) | お酒 | 10% | 酒税法の対象 |
| レストランでの飲食、喫茶店での飲食 | 10% | 外食は対象外 | |
| テイクアウト、出前、宅配サービスの容器代、配達料金 | 10% | 飲食料品と明確に区分できる場合を除く |
外食の線引きは?

日々の暮らしの中で、飲食店を利用する機会は多いでしょう。しかし、消費税の軽減税率が適用される場合と、そうでない場合があることをご存知でしょうか? これは、飲食の提供形態によって「外食」と「持ち帰り」に分類されるためです。
では、一体どのような場合に「外食」とみなされるのでしょうか? 「外食」とは、レストランやカフェ、居酒屋など、お店側が用意した場所で食事を提供するサービスを指します。 例えば、レストランでゆっくりと食事を楽しむ場合や、カフェでコーヒーやケーキをいただく場合、居酒屋で仕事帰りに一杯楽しむ場合などが「外食」に該当し、10%の消費税が適用されます。
また、「外食」には、お店で食事を提供するサービス以外にも、ケータリングやイベント会場での飲食物の提供も含まれます。 一方で、テイクアウトやデリバリーのように、お店で購入した商品を持ち帰って自宅や職場などで食べる場合は、「持ち帰り」に分類され、軽減税率の対象となるため、消費税は8%となります。
このように、飲食店の利用方法によって適用される消費税率が異なるため、注意が必要です。
軽減税率導入の目的

– 軽減税率導入の目的消費税は、所得にかかわらず一律に課税されるため、所得が低い人ほど負担感が大きくなってしまいます。そこで、消費税率引き上げによる低所得者層への影響を緩和し、消費活動の冷え込みを抑制するために軽減税率が導入されました。軽減税率の対象として選ばれたのは、生活に欠かせない食料品と、日々の情報収集に重要な役割を果たす新聞です。これらの品目は、所得が低い人ほど支出に占める割合が高いため、軽減税率を適用することで、家計への負担を和らげることができます。軽減税率導入の効果としては、まず、低所得者層の生活を守るという点があげられます。消費税率引き上げによって支出が増えても、軽減税率によってその負担を軽減することができます。また、消費の落ち込みを抑制することで、日本経済全体の停滞も防ぐことができると期待されています。しかし、軽減税率導入による影響は、対象品目の線引きや事業者側の事務負担増加など、様々な課題も指摘されています。軽減税率制度の効果を最大限に引き出すためには、これらの課題に対して適切な対策を講じていく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 軽減税率導入の目的 | – 消費税は所得にかかわらず一律課税のため、低所得者ほど負担感が大きい – 消費税率引き上げによる低所得者層への影響緩和と消費活動の冷え込み抑制 |
| 軽減税率の対象 | – 生活に欠かせない食料品 – 日々の情報収集に重要な役割を果たす新聞 – (理由) 所得が低い人ほど支出に占める割合が高いため、家計への負担を和らげることができる |
| 軽減税率導入の効果 | – 低所得者層の生活を守る – 消費の落ち込みを抑制し、日本経済全体の停滞を抑制 |
| 軽減税率導入による課題 | – 対象品目の線引き – 事業者の事務負担増加 |
