システム開発における「非機能要件」とは?

ICTを知りたい
先生、『非機能』ってよく聞くんですけど、具体的にどんなことですか?

ICT研究家
なるほどね。『非機能』は『非機能要件』の略で、システムがちゃんと動くための機能以外の大切な要素のことだよ。例えば、使いやすさや安全対策、災害が起きた時の備えなどが挙げられるよ。

ICTを知りたい
機能以外の要素…ですか? なんとなくイメージが掴めないです…

ICT研究家
例えば、みんなが使っているこのメッセージアプリで考えてみよう。メッセージを送れる機能は重要だけど、それ以外に、もし災害で停電になってもメッセージの履歴が残っていることや、他の人に見られないように情報が守られていることも大切だよね?こうした機能以外の要素が『非機能』なんだよ。
非機能とは。
情報通信技術に関する言葉で、「非機能」というものがあります。これは、「非機能要件」を短くした言い方で、システムがちゃんと動くために必要な、機能以外の部分を指します。具体的には、次のようなものがあります。
* -使い続けられるか-: システムが壊れずに動き続けられるか、災害が起きても大丈夫かなど、安心して使い続けられるための条件
* -どのくらい速く動くか-: システムがどのくらいの速さで情報を処理できるか、将来システムを大きくするときはどうかなど、システムの性能に関する条件
* -扱いやすいか-: 普段の使い方や、問題が起きたときの対処など、システムを管理しやすくするための条件
* -他のシステムに移せるか-: いつ、どのように他のシステムにデータを入れ替えるかなど、システムを入れ替える際の条件
* -安全性は-: 情報漏洩などの危険にどう対応するか、データをどのように隠すかなど、情報の安全を守るための条件
* -環境への配慮-: どのような規格に合わせるか、機器をどこに置くかなど、環境に関する条件
非機能要件の概要

– 非機能要件の概要システム開発を行う上で、顧客が本当に必要としているものを理解し、実現することは非常に重要です。システムにどのような機能を搭載するべきかを決める「機能要件」と並んで、システムの品質や性能を左右する「非機能要件」にも注意を払う必要があります。機能要件は、ユーザーがシステムを使って「何ができるか」「どのような機能が実現するか」を具体的に示すものです。例えば、ECサイトであれば「商品を検索する」「カートに入れる」「購入手続きを行う」といった機能が挙げられます。一方、非機能要件は、システムが「どのように動作するか」「機能がどれくらい快適に使えるか」といった、機能以外の側面に関する要件を指します。具体的には、処理速度、セキュリティの強さ、システムの安定性、操作性の良さなどが挙げられます。非機能要件が満たされていない場合、たとえ機能要件を満たしていたとしても、ユーザーはシステムに対して不満を抱く可能性があります。例えば、ECサイトで商品を購入しようとした際に、処理が遅くてなかなか手続きが進まなかったり、セキュリティに不安を感じたりすると、ユーザーはサイトの利用を諦めてしまうかもしれません。非機能要件を明確化し、開発の初期段階からしっかりと組み込むことで、システムの安定性、使いやすさ、安全性を向上させることができます。その結果、ユーザーの満足度を高め、システムの価値を高めることに繋がります。非機能要件は、システム開発における重要な要素と言えるでしょう。
| 分類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 機能要件 | ユーザーがシステムを使って「何ができるか」「どのような機能が実現するか」 | ECサイトで「商品を検索する」「カートに入れる」「購入手続きを行う」 |
| 非機能要件 | システムが「どのように動作するか」「機能がどれくらい快適に使えるか」といった、機能以外の側面に関する要件 | 処理速度、セキュリティの強さ、システムの安定性、操作性の良さ |
非機能要件の種類:可用性

システム開発において、利用者の期待に応えるためには、機能的な完成度だけでなく、安定性や信頼性といった要素も同様に重要となります。これを「非機能要件」と呼びますが、その中でも「可用性」は、システムが利用者の要求に応じて正常に動作し続ける能力を指します。
「可用性」が高いシステムとは、予期せぬトラブルや障害が発生した場合でも、システムの停止時間やサービスの中断時間を最小限に抑え、利用者への影響を最小限に抑えることができるシステムのことを指します。
例えば、大規模な地震が発生した場合でも、重要なデータが失われないように、あらかじめ遠隔地にデータを複製しておく仕組みや、システムの一部に障害が発生した場合でも、他の部分が肩代わりして動作を継続できるような仕組みが必要となります。
また、障害発生時には、迅速な復旧体制も重要です。あらかじめ復旧手順を定め、定期的に訓練を行うことで、復旧時間を短縮し、業務への影響を最小限に抑えることができます。
このように、「可用性」を向上させるためには、様々な対策を講じる必要があります。システムの設計段階から、想定されるリスクを洗い出し、適切な対策を施すことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | システムが利用者の要求に応じて正常に動作し続ける能力 |
| 高い可用性とは | 予期せぬトラブルや障害が発生した場合でも、システムの停止時間やサービスの中断時間を最小限に抑え、利用者への影響を最小限に抑えることができること |
| 具体例 | – データの遠隔地複製 – システムの冗長化構成 – 迅速な復旧体制の構築と訓練 |
| 設計段階での考慮事項 | 想定されるリスクの洗い出しと適切な対策 |
非機能要件の種類:性能・拡張性
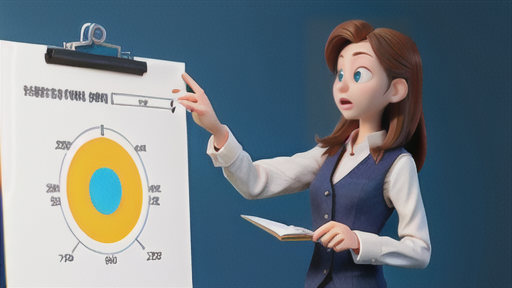
– 非機能要件の種類性能・拡張性情報システム開発において、ユーザーの要望を満たすためには、機能的な側面だけでなく、使いやすさや安定性といった機能以外の側面も考慮する必要があります。これらの機能以外の側面を「非機能要件」と呼びます。「性能」と「拡張性」は、この非機能要件の中でも特に重要な要素です。「性能」とは、システムがユーザーの要求に対して、どれほど迅速に処理を実行できるかという能力を示すものです。求められる処理速度や応答時間などは、システムの用途や利用状況によって異なります。例えば、リアルタイム処理が求められる金融取引システムでは、ミリ秒単位での高速処理が求められます。一方、社内業務システムであれば、数秒程度の応答時間でも許容される場合があります。「拡張性」とは、将来的なシステムの拡張や変更に柔軟に対応できる能力を指します。システム開発当初は想定していなかったユーザー数の増加やデータ量の増大、新たな機能追加などが発生する可能性があります。このような変化に柔軟に対応できるシステム設計をしておくことが重要です。例えば、ユーザー数が増加した場合でも、システムの処理能力を維持できるように、サーバーを増設できるような仕組みを導入しておくことが考えられます。性能と拡張性は、システムの信頼性やユーザー満足度に直結する重要な要素です。システム開発の初期段階から、これらの要件を明確に定義し、システム設計に反映させることが、プロジェクト成功の鍵となります。
| 非機能要件 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 性能 | システムがユーザーの要求に対して、どれほど迅速に処理を実行できるかという能力 | – リアルタイム処理が求められる金融取引システムでは、ミリ秒単位での高速処理 – 社内業務システムであれば、数秒程度の応答時間 |
| 拡張性 | 将来的なシステムの拡張や変更に柔軟に対応できる能力 | ユーザー数が増加した場合でも、システムの処理能力を維持できるように、サーバーを増設できる仕組み |
非機能要件の種類:運用・保守性

– 非機能要件の種類運用・保守性情報通信技術において、システム開発の成功には利用者の目に見える機能だけでなく、円滑な運用や保守を支える要素も重要です。これを「運用・保守性」と呼びます。これは、システムを問題なく安定的に稼働させ続けると同時に、変更や改善に柔軟に対応できるかどうかに大きく関わってきます。運用・保守性を高めるためには、開発段階から様々な工夫を凝らす必要があります。例えば、システムの状態を常に把握するための監視機能は、問題発生を早期に発見し、迅速な対応を可能にします。また、障害発生時には、原因究明を容易にする詳細なログ取得機能が役立ちます。さらに、システム管理者が使いやすいように設計された分かりやすい管理画面は、日々の運用作業やバージョンアップ作業を効率化し、担当者の負担を軽減します。このように、運用・保守性を考慮したシステム開発は、システムの安定稼働に繋がり、予期せぬトラブルによる損失を最小限に抑えることができます。さらに、運用・保守の負荷を軽減することで、人件費などのコスト削減にも貢献します。結果として、利用者にとってより良いサービス提供を実現できるのです。
| 非機能要件の種類 | 運用・保守性 |
|---|---|
| 目的 | システムを – 問題なく安定的に稼働させ続ける – 変更や改善に柔軟に対応できる |
| 具体的な工夫点 | – 監視機能 – 詳細なログ取得機能 – 分かりやすい管理画面 |
| メリット | – システムの安定稼働 – 人件費などのコスト削減 |
非機能要件の種類:移行性

– 非機能要件の種類移行性システム開発において、機能と同じくらい重要なのが「非機能要件」です。その中でも「移行性」は、開発時の設計や実装によって大きく影響を受ける要素の一つです。移行性とは、既存のシステムから新しいシステムへ、あるいは将来的なシステム更改の際に、スムーズに移行できるかどうかを表す指標です。ここでの「スムーズさ」は、移行にかかる時間、費用、そして業務への影響度合いによって測られます。例えば、長年使い続けてきたシステムがあるとします。そのシステム内に蓄積された大量のデータを新しいシステムに移行するには、データ形式の変換や整合性の確認など、多くの時間と労力を要します。また、システム間でデータのやり取りを行うためのインターフェースが適切に設計されていない場合、互換性の問題が発生し、移行作業がさらに複雑化する可能性もあります。移行性を高めるためには、システム開発の初期段階からデータ形式の標準化やシステム間インターフェースの設計に配慮することが重要です。データ形式を統一することで、データ変換の手間を省き、移行作業を効率化できます。また、汎用性の高いインターフェースを採用することで、将来的なシステム変更にも柔軟に対応できるようになります。スムーズな移行は、単に時間や費用を抑えるだけでなく、業務中断のリスクを最小限に抑え、企業の安定的な事業継続を支える上でも非常に重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移行性とは | 既存システムから新しいシステム、または将来のシステム更改への円滑な移行を指す指標。時間、費用、業務への影響度で評価される。 |
| 移行性を阻害する要因 | データ形式の不一致、システム間インターフェースの設計不良など。 |
| 移行性を高めるための対策 | データ形式の標準化、汎用性の高いシステム間インターフェースの設計など。 |
| スムーズな移行のメリット | 時間と費用の削減、業務中断リスクの最小化、企業の安定的な事業継続を支援。 |
非機能要件の種類:セキュリティ

– 非機能要件の種類セキュリティシステム開発において、どのような機能を実現するかはもちろん重要ですが、それと同じくらい重要なのが「機能しないこと」を決めることです。これを非機能要件と呼びます。その中でも「セキュリティ」は、開発されたシステムやそのシステムが扱うデータを、情報漏えいや不正アクセスといった脅威から保護するための要件です。特に、個人情報や企業秘密など、取り扱いに注意が必要な重要な情報を扱うシステムでは、セキュリティ対策は非常に重要となります。もしも、このような情報が漏えいしてしまったら、利用者の信頼を失墜させるだけでなく、法律に違反してしまう可能性もあるからです。強固なセキュリティ対策を実現するためには、多層的なアプローチが欠かせません。例えば、アクセス制御によって許可された人だけがシステムにアクセスできるようにしたり、データの暗号化によって情報の内容を第三者に読めなくしたりする対策が考えられます。さらに、システムの脆弱性を定期的に発見・修正することも重要です。このように、セキュリティ対策はシステムの信頼性を担保し、安心して利用できる環境を提供するために欠かせない要素と言えるでしょう。
| 非機能要件「セキュリティ」とは | 重要性 | 具体的な対策例 |
|---|---|---|
| 開発されたシステムやデータを、情報漏えいや不正アクセスといった脅威から保護するための要件 | – 特に個人情報や企業秘密など重要な情報を扱うシステムでは非常に重要 – 情報漏えいは、利用者の信頼を失墜、法律違反の可能性も |
– アクセス制御 – データの暗号化 – システムの脆弱性の定期的な発見・修正 |
非機能要件の種類:環境・エコロジー

– 非機能要件の種類環境・エコロジー現代社会において、環境への配慮はシステム開発においても重要な要素となっています。これは従来の機能性や使いやすさといった側面に加えて、地球全体の持続可能性を考慮したシステム作りが求められているからです。環境・エコロジーに関する非機能要件としては、省エネルギー化が挙げられます。情報システムは多くの電力を消費するため、システム全体や個々の機器の電力効率を高めることが重要です。例えば、サーバーやネットワーク機器の省電力化、運用時間外におけるシステムの一部停止など、様々な角度からの工夫が求められます。また、環境負荷の低い素材の利用も重要な要素です。システム開発に使用される機器や部品には、製造過程や廃棄時に環境負荷の高い物質が含まれている場合があります。環境に配慮した素材を選択することで、資源の枯渇や環境汚染の抑制につなげることが可能です。具体的な取り組みとしては、データセンターにおける冷却効率の向上や再生可能エネルギーの利用などが挙げられます。また、システム開発の初期段階から環境負荷を考慮した設計を行うことで、より効果的な対策が可能となります。このように、環境・エコロジーへの配慮は、もはや企業の社会的責任としてだけではなく、システムの持続可能性を左右する重要な要素となっています。開発者はこの点を強く意識し、環境負荷を低減するための技術や設計手法を積極的に取り入れていく必要があります。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 省エネルギー化 | システム全体や機器の電力効率を高める | – サーバーやネットワーク機器の省電力化 – 運用時間外におけるシステムの一部停止 |
| 環境負荷の低い素材の利用 | 製造過程や廃棄時に環境負荷の高い物質を含む機器や部品の使用を避ける | – 環境に配慮した素材の選択 |
| その他 | データセンターにおける環境負荷低減 | – 冷却効率の向上 – 再生可能エネルギーの利用 |
