製造業だけじゃない!ABCでコスト管理を改善しよう

ICTを知りたい
先生、「ABC」って言葉をよく聞くんですけど、どんな意味ですか?

ICT研究家
「ABC」は、活動基準原価計算の略だよ。ものやサービスを作るのに、実際にはいくらかかっているのかを、活動ごとに細かく計算する方法なんだ。たとえば、製品を作るのに、材料を運ぶ、機械を動かす、検査をする、といった活動すべてにかかるお金を計算するんだよ。

ICTを知りたい
へー、活動ごとに計算するんですね! なんでそんな風に計算する必要があるんですか?

ICT研究家
昔は、たくさんの製品をまとめて作っていたから、材料費などの直接的な費用がほとんどだったんだ。でも、今は、いろいろな種類の製品を少しずつ作るようになって、電気代や工場の家賃といった間接的な費用が増えているんだよ。だから、活動ごとに計算して、より正確に費用を把握することが大切になってきているんだ。
ABCとは。
情報通信技術に関係する言葉で、「活動基準原価計算」というものがあります。これは、簡単に言うと、活動ごとにコストを計算する方法です。アメリカのハーバード大学のロバート・キャプラン教授が考え出した、経営管理のための計算方法です。もともとは、工場などでものを作るところで使われていました。工場では、材料費や人件費以外にも、電気代や工場の家賃など、いろいろな費用がかかります。この方法では、そうした費用を、それぞれの活動ごとに分けて計算します。今では、工場だけでなく、役所や町のサービス、コンピューター関係の費用計算など、いろいろなところで使われています。
昔は、同じ種類の製品をたくさん作るのが普通で、材料費や人件費など、製品を作るための直接的な費用の割合が多かったので、それほど問題はありませんでした。しかし、最近は、いろいろな種類の製品を少しずつ作るようになり、機械化が進んだことで、電気代や工場の家賃などの間接的な費用の割合が大きくなりました。その結果、実際の利益が減ってしまい、問題になってきました。
そこで、製品にかかるコストを正しく把握し、間接的な費用をより正確に製品に割り当てるために、活動基準原価計算が考え出されました。
活動基準原価計算は、コストを正確に把握できる方法ですが、計算結果を分析して、より良い方法を考えることが大切です。そこで、活動基準原価計算で分析した結果を使って、経営を改善する方法として、「活動基準原価管理」を行うことが求められています。
しかし、最近は、仕事が複雑になり、活動が増えたり、種類が増えたりしたことで、活動基準原価計算のモデルが複雑になってきています。そのため、活動基準原価計算に対する評価が低くなってきており、改善版として「時間駆動型活動基準原価計算」も出てきています。
ABCとは
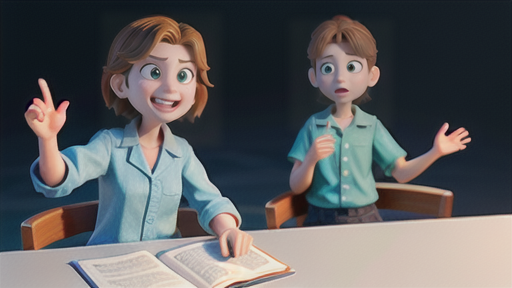
– ABCとは
ABCとは、活動基準原価計算(Activity-Based Costing)の略称で、製品やサービスなどのコストを、それを作り出すために必要な活動(activity)に基づいて計算する手法です。
従来の原価計算では、材料費や人件費などの直接費に加えて、製造にかかる間接費を、製造原価に一定の割合で按分していました。しかし、近年の製品の多様化やサービスの高度化に伴い、間接費が占める割合が大きくなっています。そのため、従来の原価計算では、製品やサービスの実際のコストを正確に把握することが難しくなってきています。
そこで、ABCでは、製品やサービスを製造するために必要な活動を洗い出し、それぞれの活動に要するコストを計算します。例えば、製品の設計、部品の調達、組み立て、検査、出荷などの活動が挙げられます。そして、それぞれの活動にどれだけの資源(人件費、材料費、設備など)が使われているかを調べ、コストを算出します。
こうして計算された活動ごとのコストを、それぞれの製品やサービスがどれだけその活動を利用したのかという配賦基準に基づいて配賦していくことで、より正確な原価計算を行います。例えば、ある製品の組み立てに要した時間が他の製品よりも長い場合は、組み立て活動のコストをより多く配賦します。
ABCを導入することで、より正確な原価情報を得ることができ、その結果、適切な価格設定、製造プロセス改善、製品戦略策定などに役立てることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 活動基準原価計算(Activity-Based Costing)の略称で、製品やサービスなどのコストを、それを作り出すために必要な活動(activity)に基づいて計算する手法 |
| 従来の原価計算の問題点 | 間接費を製造原価に一定割合で按分していたため、製品やサービスの実際のコストを正確に把握することが困難だった。 |
| ABCの特徴 | 製品やサービスを製造するために必要な活動を洗い出し、それぞれの活動に要するコストを計算する。 |
| ABCにおけるコスト計算 | それぞれの活動にどれだけの資源(人件費、材料費、設備など)が使われているかを調べ、コストを算出する。 |
| ABCにおけるコスト配賦 | 計算された活動ごとのコストを、それぞれの製品やサービスがどれだけその活動を利用したのかという配賦基準に基づいて配賦する。 |
| ABC導入のメリット | – より正確な原価情報を得ることができる – 適切な価格設定 – 製造プロセス改善 – 製品戦略策定 |
ABCが注目される背景

近年、製造業では顧客の多様なニーズに応えるため、製品の種類が増え、一品あたりの生産量は減少する傾向にあります。また、サービス業は経済の成長とともに重要性を増しており、その提供するサービスは多岐にわたっています。このような変化に伴い、従来の原価計算方法では、間接費の製品やサービスへの適切な配分が困難になりつつあります。
従来の原価計算では、製造直接費や材料費などの直接費に比べて、電気代や工場の賃借料といった間接費は、特定の製品やサービスに直接結び付けることが難しいという特徴がありました。そのため、従来は製造部門の従業員数や作業時間などを基準に間接費を配賦していました。しかし、製品の多様化やサービス業の成長により、この方法ではコストの歪みが大きくなり、正確な製品原価やサービス原価を把握することが困難になってきたのです。
そこで、近年注目されているのがABCです。ABCは、製品やサービスが実際にどのような活動(設計、製造、販売など)によって作り出されているのかを分析し、それぞれの活動に必要となる資源(人件費、材料費、設備費など)を把握します。そして、その資源を活動量(作業時間、回数など)に応じて製品やサービスに配賦することで、より正確な原価計算を実現しようとするものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製造業の現状 | 顧客ニーズの多様化により、製品の種類が増加し、一品あたりの生産量は減少傾向にある。 |
| サービス業の現状 | 経済成長とともに重要性を増しており、多様なサービスを提供している。 |
| 従来の原価計算の問題点 | 間接費の製品やサービスへの適切な配分が困難。製造部門の従業員数や作業時間などを基準に間接費を配賦していたため、コストの歪みが大きくなり、正確な原価把握が困難に。 |
| ABC (活動基準原価計算) | 製品やサービスの活動 (設計、製造、販売など) を分析し、必要な資源 (人件費、材料費、設備費など) を把握。資源を活動量 (作業時間、回数など) に応じて製品やサービスに配賦することで、より正確な原価計算を実現。 |
ABCのメリット

– ABCのメリット
従来の原価計算では、製品やサービス、あるいは工程や活動にどれだけコストがかかっているのか、正確に把握することが困難でした。そこで、資源とその消費量に基づいてコストを計算するABCを導入することで、より詳細で正確なコスト情報を得ることが可能になります。
例えば、ABCを導入すれば、特定の製品の製造にどれだけの労務費や材料費がかかっているのか、あるいは顧客対応や受発注業務といった活動にどれだけの経費が発生しているのかを、具体的に把握することができます。
ABCによって明らかになったコスト情報を活用することで、企業は収益性の低い製品やサービスの改善や廃止、コスト削減の余地のある工程や活動の見直しといった、具体的な経営改善策を講じることが可能になります。
このように、ABCは単なる原価計算の手法ではなく、企業が抱える経営課題を浮き彫りにし、その解決を支援するための強力なツールと言えるでしょう。
| 従来の原価計算の課題 | ABCの導入効果 | ABCを活用した経営改善 |
|---|---|---|
| 製品・サービス、工程・活動のコスト把握が困難 | 資源とその消費量に基づいた詳細かつ正確なコスト情報の取得が可能に | 収益性の低い製品・サービスの改善・廃止 コスト削減可能な工程・活動の見直し |
ABCの導入手順

– ABCの導入手順ABC(活動基準原価計算)を導入するためには、いくつかの段階を踏む必要があります。 まず初めに、原価計算の対象となる製品やサービスを明確に定めましょう。例えば、ある企業が複数の製品を製造している場合、どの製品をABCの対象とするのかを決定する必要があります。次に、対象となる製品やサービスを提供するために、具体的にどのような活動(業務)が発生しているのかを洗い出します。製造部門における組立作業や検査作業、営業部門における顧客訪問や見積書作成など、企業活動の全てを細かく分類し、それぞれの活動を明確に定義することが重要です。そして、それぞれの活動にどれだけの費用がかかっているのかを、人件費や材料費、設備の減価償却費なども含めて集計します。この際、従来の原価計算では見過ごされがちだった間接費についても、可能な限り活動ごとに配賦していくことが、ABC導入の大きなポイントとなります。最後に、それぞれの活動が、どの製品やサービスに、どれだけの割合で貢献しているのかを分析し、集計した活動ごとの費用を、それぞれの製品やサービスに配賦していきます。この工程を「原価の配賦」と呼びます。このように、ABCの導入には、既存の原価計算システムの見直しや、活動量などのデータ収集など、一定の時間と労力を必要とします。しかし、ABCによって、より正確な製品やサービスごとの原価を把握することができれば、その後の価格設定やコスト削減活動の精度を向上させ、企業の収益向上に大きく貢献できる可能性があります。
ABCの課題と進化

近年、従来の原価計算に比べて、より正確な原価情報を得ることができる手法として、ABCが注目されています。しかし、その一方で、導入や運用には複雑なプロセスと多大なコストが必要となる点が課題として挙げられています。
特に、業務を細かく分類しすぎると、ABCシステム自体が複雑化し、運用が困難になる可能性も孕んでいます。そこで、近年では、この課題を克服するために、ABCをより簡素化し、導入や運用を容易にする取り組みが進められています。例えば、活動の分類を必要最小限に抑えたり、システムの自動化を進めることで、効率的な運用を実現しようとする動きが見られます。
また、ABCは過去のデータに基づいて原価を計算するため、将来の環境変化に対応できないという側面も指摘されています。この点に関しても、近年では、ABCで算出した原価情報を活用して、将来の原価予測やシミュレーションを行うなど、従来の枠組みを超えた活用方法が模索されています。具体的には、過去のデータと将来予測のデータを組み合わせることで、より精度の高い原価予測を行ったり、様々な経営戦略の効果をシミュレーションしたりすることが可能となります。このように、ABCは進化を続けており、企業の経営意思決定に、より一層貢献していくことが期待されています。
| メリット | 課題 | 改善策 |
|---|---|---|
| 従来よりも正確な原価情報を取得できる |
|
|
